もしも、「ギタリストとしての人生名盤」を10枚選ぶとしたら? きっとそこには音楽性やプレイ・スタイルのみならず、何を楽しみ何に喜ぶのか、感性や視野がどう形成されたのか、どんな壁にぶつかり、どんなターニング・ポイントがあったのかなど、これまでの生き方を物語る、まさに「人生」そのものが描かれていることでしょう。それをプロに答えてもらうのが、このコーナー。記念すべき第1回は、ギタリストとして新たな境地を目指し、プロデューサーとしても多くのアーティストをサポートしている若きミュージシャンズ・ミュージシャン、岡田拓郎。新作『Morning Sun』が、各方面で高い評価を受けている彼が選んだ10枚とは?
取材=福崎敬太
王道とは違う視点でギターを考える
そもそも僕は“ギター・マガジン育ち”なんです(笑)。小学6年生の時に、ジェシ・エド・デイヴィスやエリック・クラプトン、デュアン・オールマンが載っているスライド・ギター特集号(2003年8月号)を買って読んで、ギターを始めたんですよ。で、生まれが福生の米軍基地の近くで、ブルース・セッションができる場があったので、よくリトル・フィートやザ・バンドなどを聴きながら中学生くらいまで育ったんです。だから、いわゆる王道のクラシック・ロックを経験しながらずっとギターを弾いていました。
その後、自分で音楽を作るようになった時に、人とは違うギターの響き方ってあるのかなという模索をするようになったんです。60〜70年代のベーシックなクラシック・ロックのギターではない感覚の奏法をいかに組み込むか、というか。その一連の流れが今の自分のギター観につながっていますね。
だから今回の10枚も、ギター・マガジンからの影響とは違う視点でギターをとらえた時に挙がってきた作品です。ちょっとマニアックですけど、多くは高校生の時に出会ったもので、当時は同じ歳頃のギター弾きが聴いていない音楽を知れるだけですごく楽しかったんですよ。
1/ペンタトニックの可能性を見出した1枚。
Guitar Roberts(Loren Connors)
『In Pittsburgh』(1989/St. Joan)

【アルバム解説】
現代音楽の鬼才ギタリスト、ローレン・コナーズが1989年に自主制作で残した1枚。名義は“Guitar Roberts”で、ギター1本で怪しげなムードを醸し出す。最後に収録されたロニー・ジョンソンのカバー「Blue Ghost Blues」のみスーザン・ランギールがボーカルで参加。
よくこの作品をCDで流しながら一緒にギターを弾いていました。これはアナログでずっと欲しかった1枚で、初めて自分のアルバムが売れた時の印税でオリジナル盤を買ったんですよ。レフトフィールド(推進的)なギタリストの中ではかなりブルース的なので、クラプトンとかを聴くような感覚でけっこうすんなり入れました。
ペンタトニックの音だけなのに、こんなに豊かに響くということに感動して。おこがましいですけど、良い意味で“これなら自分でも表現できるな”と思えたんです。ブルース的な指使いが染み込んでしまっている自分でも、聴いたことのないギター・サウンドが生み出せるかもしれない、という指標になる1枚でしたね。
あと、今でこそ配信ライブはよくやっていますけど、僕が初めてそれで観たのはローレン・コナーズなんですよ。渋谷のWWWでの灰野敬二さんとのデュオだったんですけど、ローレンはご病気で飛行機とかに乗れなくて来日できないから、その当時はめずらしいオンラインでのセッションになったんです。
灰野さんはライブハウスでリアルに演奏されるんですけど、ステージの横に備え付けられたモニターの中でローレンは演奏していて。それがとても印象に残っていて、最近ふとそのことを思い出したりしています。
2/岡田もカバーした、隠れリゾート名盤。
Steve Hiett
『Down On The Road By The Beach』(1983/CBS/Sony)

【アルバム解説】
イギリスの写真家であるスティーヴ・ハイエットが1983年に残した作品で、邦題は『渚にて』。トレモロがかったハイファイなギター・サウンドが80年代のリゾート感を醸し出す。岡田は『The Beach EP』で本作収録の「By The Pool」をカバーしている。
僕がこの作品を知った2016年頃は、エレクトロな音楽に対してギターは古いものだっていう感覚が作り手にあった時期だと思うんです。でも、フランク・オーシャンの『ブロンド』(2016)やジ・インターネットの『エゴ・デス』(2015)あたりを聴くと“けっこうギター・アルバムじゃん”って思って。
で、僕は気に入った新譜があった時に、それに近い過去のアルバムをディグるのが趣味なんですが、『ブロンド』のハーフトーンの浮遊感のあるフワッとした感じの音を探していたんです。それでYouTubeで偶然この作品を見つけて。ギターでどんな音楽を作るのかを迷っていた時に出会った1枚で、人生で初めて人の曲をカバーしたくらい好きな作品です(「By The Pool」/『The Beach EP』収録)。
彼もたぶんブルース・ロックが好きな人だと思うんですよ。ただ、宅録で作った感じと当時の音響感が合わさって、意図せず今日っぽくなった、けっこうミラクルなアルバム(笑)。あと、彼は写真家としてすごく有名な人で、彼の写真を借りるのはなかなかハードルが高いのですが、僕が彼の楽曲をカバーしたのをすごく喜んでくれて、そのドサクサに紛れてジャケットで写真を使う事を快諾してくれたんです(笑)。
3/アンビエントな雰囲気をギター的サウンドで。
Burkhard Stangl
『Unfinished. For William Turner, Painter.』(2013/Touch)

【アルバム解説】
即興音楽のフィールドで高い評価を集める、オランダのギタリスト=ブルクハルト・シュタングル。2013年にリリースされた本作は、ほぼギターのみで奥行きのある音像を生み出した意欲作だ。弦の擦れる生々しい音まで表現の一部としてコントロールしている。
実験音楽やフリー・インプロの現場に出入りしていた頃、 “おもしろい音”を作るっていうところに魅力を感じていたんです。
それに加えてクリスチャン・フェネスなどのエレクトロニカにも影響を受けて、所謂ギターが持つ特性からはずれた音を出すことにすごく魅了されていた時期で。
そういう頃に出会ったこのアルバムは、1曲が30〜40分あって実験的でアンビエントな感じなんですけど、極めてギター的な演奏なんですよ。でも、そういう素のギター・サウンドで、こういう詩情をはらんだ作品を作ることができるんだっていうことに驚いて。どうやっているのか詳しくはわからないんですが、レコードのパチパチするノイズのような音をアンプに付いているスプリング・リバーブだけで演奏していたり。“ツイン・リバーブを演奏するっていう概念があるんだ”って驚愕しましたね(笑)。
プリペアドでもテーブル・トップ・ギターでもなく、エフェクトはトレモロとリバーブ、あとはちょっとフェイザーが入っているくらいで、基本的にはツイン・リバーブ(みたいなシンプルなアンプ)とエレキ・ギター1本だけでこんな表現ができることにすごく感動したんですよ。
ギターという楽器はタッチやアーティキュレーションだけでこんなにも大きい表現ができると、改めて気付かされた1枚ですね。
4/ジャズの中でも“弾かない”美学。
Jakob Bro
『December Song』(2013/Loveland Records)
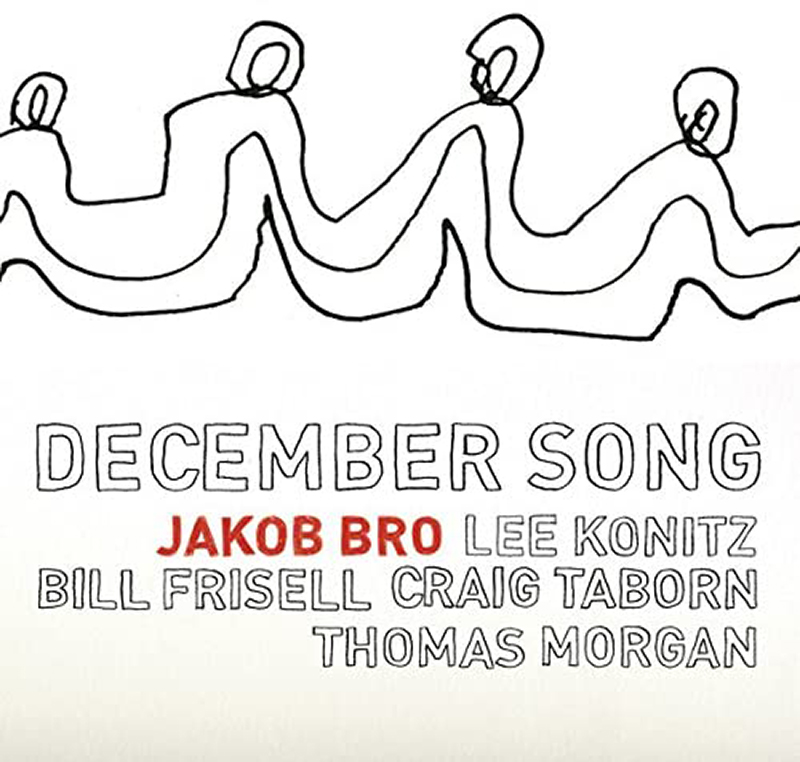
【アルバム解説】
コペンハーゲン在住のギタリスト、ヤコブ・ブロ。本作は『Balladeering』(09年)、『Time』(11年)から連なる三部作のラストで、ニューヨークで録音された。アルト・サックスの巨匠リー・コニッツや、ビル・フリゼールらの参加もトピックに。
ジャズを演奏したい気持ちは常にあるんですよ。で、自分のプレイに取り入れられるジャズ・ギタリストって、ECMのギタリストがけっこう多くて。
このヤコブ・ブロもそうだし、テリエ・リピダルやデヴィッド・トーン、ビル・フリゼール、弟のアルバムに参加する形で80年代にECMから出しているネルス・クラインもしかり。
その中で、“この速さのジャズなら弾ける気がする”と思ってヤコブにハマっていったんですけど、なんとも真似しづらいギタリストだなと……。“こんなに弾かないのは逆に難しいな”って思ったんですよね。でも、こういうジャズ的なアンサンブルの対話がある即興演奏の中で、ここまで弾かないギタリストに“なんて禁欲的で美しいんだ”とも思ったんです。
アンサンブルで煽られればついつい弾きたくなるけど、特にギターは弾きすぎてしまうとどこかクラシック・ロックのようになってしまうし、それをいかに回避するかっていうのは自分の命題でもあって…多くの人はなぜそんな風に僕が考えるか理解してもらえないと思うけど…(笑)。ジャム・セッションも楽しいですけど、僕はどちらかと言うと静かだけど低温火傷しそうなアンサンブルに関心があります。
もちろんチョーキングして得られるカタルシスも最高だけど、基本的にはしたくない。そういう“弾かないギタリスト”のモデルとして、一番的確に弾かない人はヤコブ・ブロだなっていう感じがしますね。
5/ロジカルな場面でもパッションで押し切る強さ。
Daniel Lanois
『Belladonna』(2005/Epitaph)
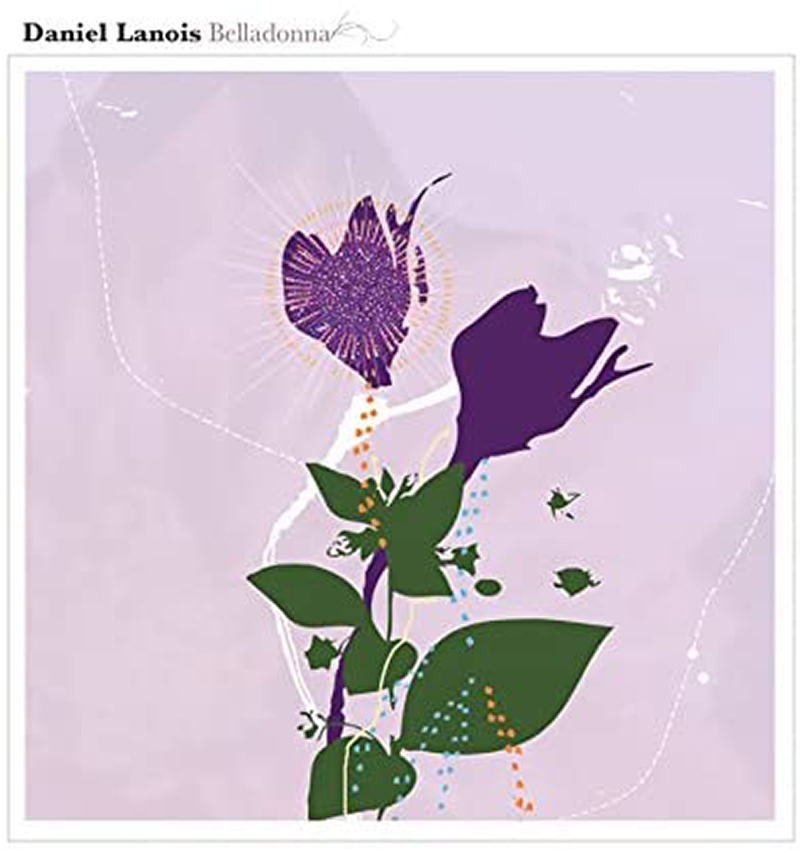
【アルバム解説】
U2やピーター・ガブリエルなど、多くのビッグネームとの仕事で知られるダニエル・ラノワ。本作はスティール・ギターを軸にしたインスト・アルバムで、ブライアン・イーノのような洗練されたアンビエントと、アメリカ南部のルーツ・ミュージックを融合させた。
これはほかに挙げた作品と打って変わって、バイブスが好きなだけです(笑)。
特に彼が弾くペダル・スティールが好きなんですよ。カントリー出身の職人系のペダル・スティールも素晴らしいですけど、僕が好きなのはジェリー・ガルシアが弾いているような、わりとゆるいけどよく歌うペダル・スティールで。ラノワもそういうロックな考え方の人だと思うんですよね。
彼はディランやブライアン・ブレイドといったフィジカルなミュージシャンのプロデュースもしているけど、同時にブライアン・イーノとのアンビエント・アルバム『Apollo』(1983)にも参加しています。ギター・プレイについても、ロジカルになりそうなところも彼はパッションで突き通す。そういうところがすごく好きなんですよね。例えば“あの感じだよ! わかるでしょ!”だけで話が通じるタイプ(笑)。彼のギター性がプロデュース・ワークやミキシングにも反映されていると感じるんです。
彼の特徴的なレコードにおける部屋の奥行きの作り方は、ロジックというよりは、それこそフィーリングの部分だと思います。彼自身はパッションの人だけど、理論的なブライアン・イーノとも渡り合えるし、ボブ・ディランとも渡り合える。いろんなところで渡り合えるキャラクターなんだと思うんですよ。それは彼の自伝(『ソウル・マイニング』みすず書房刊)を読んだらわかるんですが、ちゃんと捻くれてるけどめちゃくちゃ素直な人だと思います。
6/絶妙なピッチ感のスライドが持つ魔力。
Michael Bloomfield
『Blues Gospel & Ragtime Guitar Instrumentals』(1993/Shanachie)
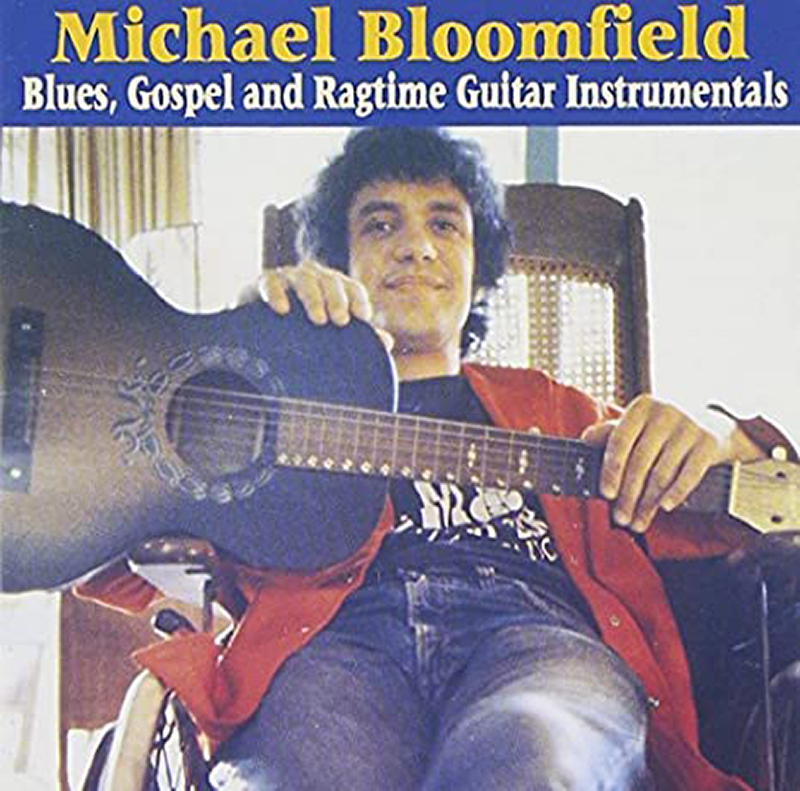
【アルバム解説】
ホワイト・ブルーズの巨匠、マイク・ブルームフィールド。本作はインスト曲のアウト・テイクを集めたもので、彼の死後にリリースされた。アルバム・タイトルのとおりゴスペルやラグタイムなどゆったりとした楽曲が並び、リラックスした音世界を堪能できる。
小学6年生の時、ギター・マガジンで紹介されていたボブ・ディランの『追憶のハイウェイ61』とフィルモアのライブ盤(『フィルモアの奇蹟』)で初めてマイク・ブルームフィールドのギターを聴いたんです。
その時、ピッチが悪い、かなり不良なギターだと思って(笑)。それまでにテレビやラジオで耳にしていた音楽のどれとも似ていない、かなり衝撃的な出会いでした。
このアルバムのスライドもまたピッチ感が泣けますね(笑)。これの「When I Need You」とかゴスペル・ナンバーがすごく好きで。ブラインド・ブレイクのような「Blake’s Rag」が入っていたりもするんですが、それよりもやっぱりスライド・ギター。これになぜグッと来るのか、本当に昔も今もうまく言葉にはできないんですよ。
僕はずっとブルースが好きでしたが、10代の頃 ブルースの歴史を知れば知るほど“日本人がブルースを弾く”ということがなんだか掛け違えたボタンのように思えた事がありました。
その時、“ユダヤ系のマイク・ブルームフィールドは子供の頃からブルースに取り憑かれて地元シカゴの黒人コミュニティに入って、腕だけで勝負していった紛れもないブルース・ギタリストだ”というエピソードに興味を持って、おこがましいですが勇気づけられる所もあって。これは手放しに日本人でもアメリカ人でも垣根なくブルースでもポップスでもやろうよ!っていう牧歌的な話ではないと思います。
当たり前ですが、僕たちは先人たちの歴史とスタイルと葛藤の積み重ねの上にいますからね。
7/アメリカの底力を感じるカントリー・アルバム。
Buddy Miller
『Buddy Miller’s Majestic Silver Strings』(2011/New West Records)

【アルバム解説】
カントリー・シンガー=バディ・ミラーが“マジェスティック・シルバー・ストリングス”名義のバックを従えた2011年作。ギターはビル・フリゼール、マーク・リボーなどが参加。「No Good Lover」などで聴けるマークのカントリー・リックは非常に興味深い。
マーク・リーボウとビル・フリゼールのふたりが参加していて、ふたりまとめて好きっていうことが言えるから選びました(笑)。
やっぱりアメリカのフォークやブルース、カントリーを“今日的にやっている”人に僕はすごく感心があるんですよ。その中でギタリスト的な大きな指標になるのが、マーク・リーボウとビル・フリゼール。この作品はビルの歌伴奏の最上の瞬間が収められたアルバムでもあるなと思っていて。いつもはどうやっても目立つマーク・リーボウがビートを転がすシェイカーのような地味なバッキングをしていたり。むしろこのふたりのギタリストを差し置いて、バディ・ミラーが弾くギター・ソロがけっこう良かったりするんですよ。そこにアメリカの底力を感じますよね(笑)。
実はもともとバディ・ミラーには全然興味がなくて(笑)、このふたりが参加していたから出会った作品なんですよ。10代の頃はジェシ・エド・デイヴィスやダニー・クーチ(コーチマー)といった好きなギタリストがセッションマンとして参加したレコードを追いかけながらいろんな作品と出会いました。
現代のアメリカにも良いセッション・ギタリストはいっぱいいるから、参加作なども常にチェックしています。今は気になったギタリストのセッション仕事なども全部ネットで簡単に見られるから良いですよね。
8/ヒューバート・サムリンを追いかけた少年時代。
Howlin’ Wolf
『Howlin’ Wolf』(1962/Chess)
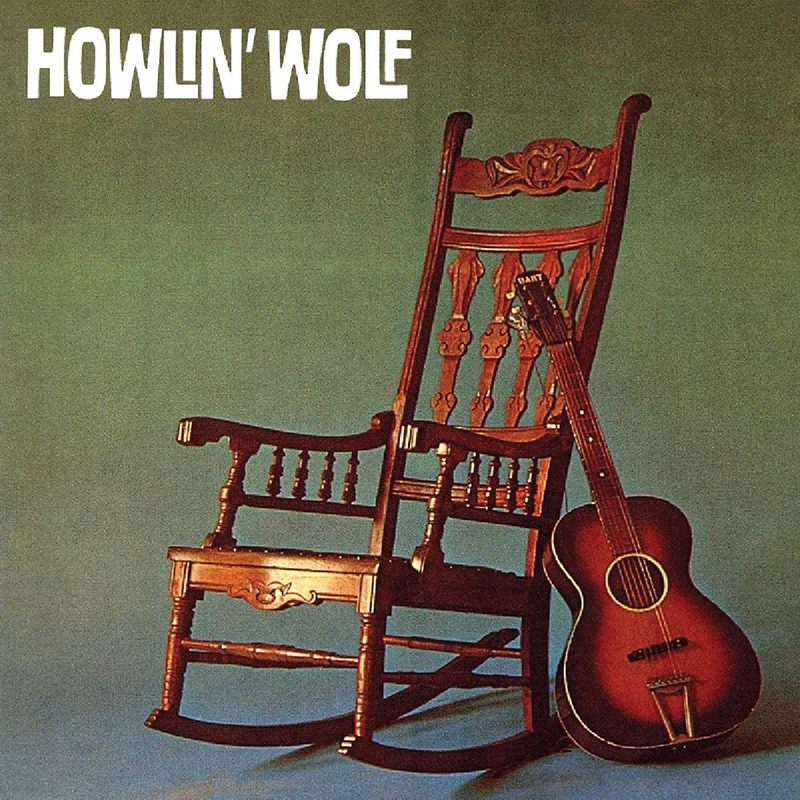
【アルバム解説】
ハウリン・ウルフのセルフ・タイトル作で、1962年発表の2nd。通称“ザ・ロッキン・チェア・アルバム”。「Spoonful」などのブルース名曲が収録された、文句なしの名盤だ。ギターはヒューバート・サムリンのほか、ジミー・ロジャースなども参加している。
10代の頃は本当にブルースばかり聴いていました。多分、当時東京都の中学生で最もブルースを聴いていたひとりだと思いますよ(笑)。
クラプトンやレイ・ヴォーンなんかが入り口になって、彼らがフェイバリットに挙げる作品を片っぱしから聴きました。ヒューバート・サムリンとマジック・サム、ブラインド・ウィリー・ジョンソンがフェイバリットでしたね。嫌な子供だったので、“三大キングはモダンすぎるね”とか言っていて(笑)。
その中でも特にヒューバート・サムリンが大好きで、ハウリン・ウルフを流してひたすらフレーズを追いかけていました。彼のリックはとてもシンプルですが、弦が輪ゴムみたいに感じるベンドや、グリス・アップ・ダウン、そして的確に押し引きする鋭くて鈍いタイムの置き方はとても勉強になりました。コーネル・デュプリーのグルーヴも近いところがありますよね。ヒューバートの真空管が飽和した鼻詰まりなトーンもかっこ良いです。
ブレイク・ミルズの作るギター・トーンは、これを手本に現代のハイ・ビットな録音環境で立体的に奥行きを持たせているように感じます。そういった意味ではこの作品のブーミーなギターの音色は今でもオルタナティブな可能性も感じますよね。
9/新しいギター奏法の指標。
Dirty Projectors
『Bitte Orca』(2009/Domino/Hostess)
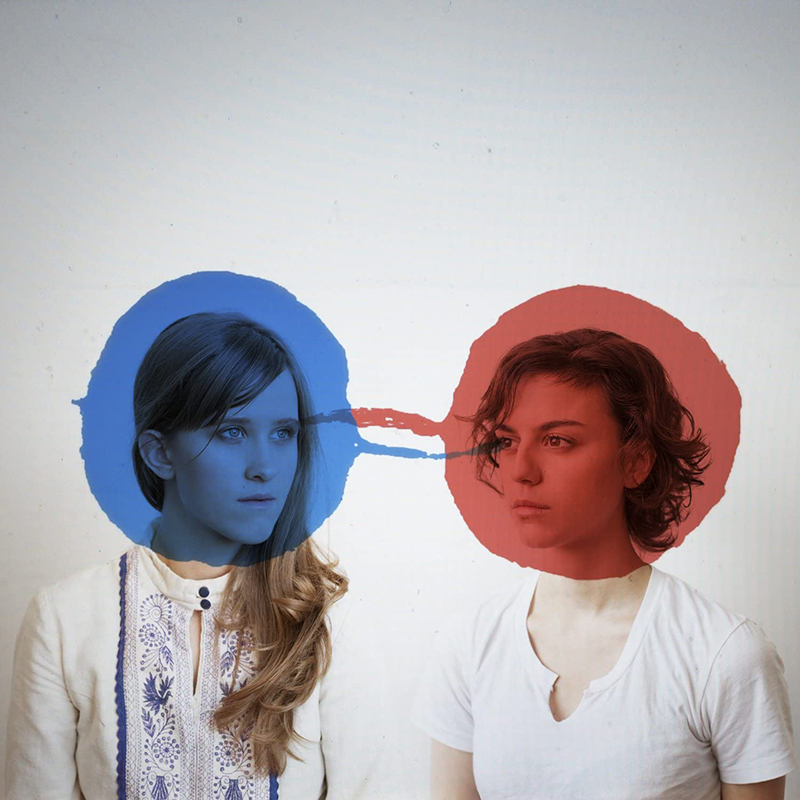
【アルバム解説】
ポップ・ミュージックを土台にしつつも、フォーク、ソウル、ゴスペル、アフロ・ビートなどなど、あらゆる要素を取り入れ、多くのリスナーに衝撃を与えたダーティ・プロジェクターズの5枚目。2000年代を代表する名盤として、さまざまなミュージシャンに影響を与え続けている。
ダーティー・プロジェクターズのデイヴ・ロングストレスは、革新的な奏法を用いているギタリストとして現在最も評価されていない人だと思っているんです。
本来ならトム・モレロやジョニー・グリーンウッドの次に語られるべき人ですよ。
ロックの更新は、サイケでもニューウェイヴでもグランジでも、新しいギターの奏法や音色と密接で、この作品は、リアルタイムで聴いたレコードで初めてそうした感動がありました。どうやっているのかわからない奏法やアイディアがこの1枚にたくさん詰まっていて。多分、コンポーザーやフロントマンとしてのイメージがあるから、ギタリストとして語られることは少ないんですけどね。
彼はフォークやハイライフ、ポストパンクのギター奏法をフィジカルのアイディアやエフェクトでひたすら過激にしたことで新しさを生んだ人だと思うんです。過激だけれどそうした文脈的な所にもインテリジェンスを感じました。ワーミーの使い方も「まだこんな使い方あったんだ!」と思うくらいぶっ飛んでるけどかなりポップな落とし方で、キャッチーなフレーズを弾く。そういうのがすごくうまい人だなと思います。
デイヴ・ロングストレスと、グリズリー・ベアのダニエル・ロッセンっていうギタリストのふたりが、僕の中で“自分世代の新しいギター奏法の指標”的な存在でした。
10/40年代の大衆音楽の匂いを感じる。
Blake Mills
『Mutable Set』(2020/New Deal Records/Verve)

【アルバム解説】
アラバマ・シェイクス『Sound & Color』のプロデュースを手がけたことで、一躍世界の注目を集めたブレイク・ミルズが今年リリースした4枚目のソロ・アルバム。彼のギターの腕前はエリック・クラプトンやジャクソン・ブラウンなどからも絶賛されている。
ブレイク・ミルズは“録音物”というものに対してかなり自覚的で、かつ新しい視点を常に持ち続けている。で、このアルバムは今までのデレク・トラックス的なスライドとか、60〜70年代のギター的な奏法をすごく丁寧に回避してエレキ・ギターを弾いていると思うんです。
あれだけ弾ける人が、ギターにおける“ギター性”を捨てて、こういう弾き方をするんだって。すごいとか良いっていうよりも、興味深いなと思いましたね。
で、楽曲から所謂60年代〜70年代性はあまり感じないけれど、それはつまり今日のギター・ミュージックの多くがいかに60年代〜70年代的なイディオム前提で成り立っているのか。という事を改めて考えさせられました。そしてこの作品から戦前のフォークやブルース、40年代の大衆音楽の匂いを感じました。
以前、取材で細野晴臣さんとアンビエントの話をする機会があったんですが、最後に“みんな40年代の音楽を忘れているよ”っていう言葉を呟かれていて(笑)。その言葉が頭をぐるぐるしていたんです。たしかにデューク・エリントンやレイモンド・スコットを今聴くとかなり興味深くて、現代の音楽とは違う概念の自由さがあるんですよね。そういう話があった直後にこの作品が出たんですけど、聴いた瞬間 “あ、40年代を覚えている人がいた”って思ったんです。
新しい質感もあるけど、ジョージ・ガーシュウィンような質感もある。ただ、60〜70年代の“ギターらしすぎる楽曲性”が丁寧に取り除かれていると感じるんです。
岡田拓郎
おかだ・たくろう◎1991年生まれ、東京都出身。2012年に“森は生きている”のギタリストとして活動を開始。2015年にバンドを解散したのち、2017年に『ノスタルジア』でソロ活動を始動させた。現在はソロのほか、プロデューサーとしても多方面で活躍中。
最新作

『Morning Sun』岡田拓郎
only in dream/ODCP-023/発売中






