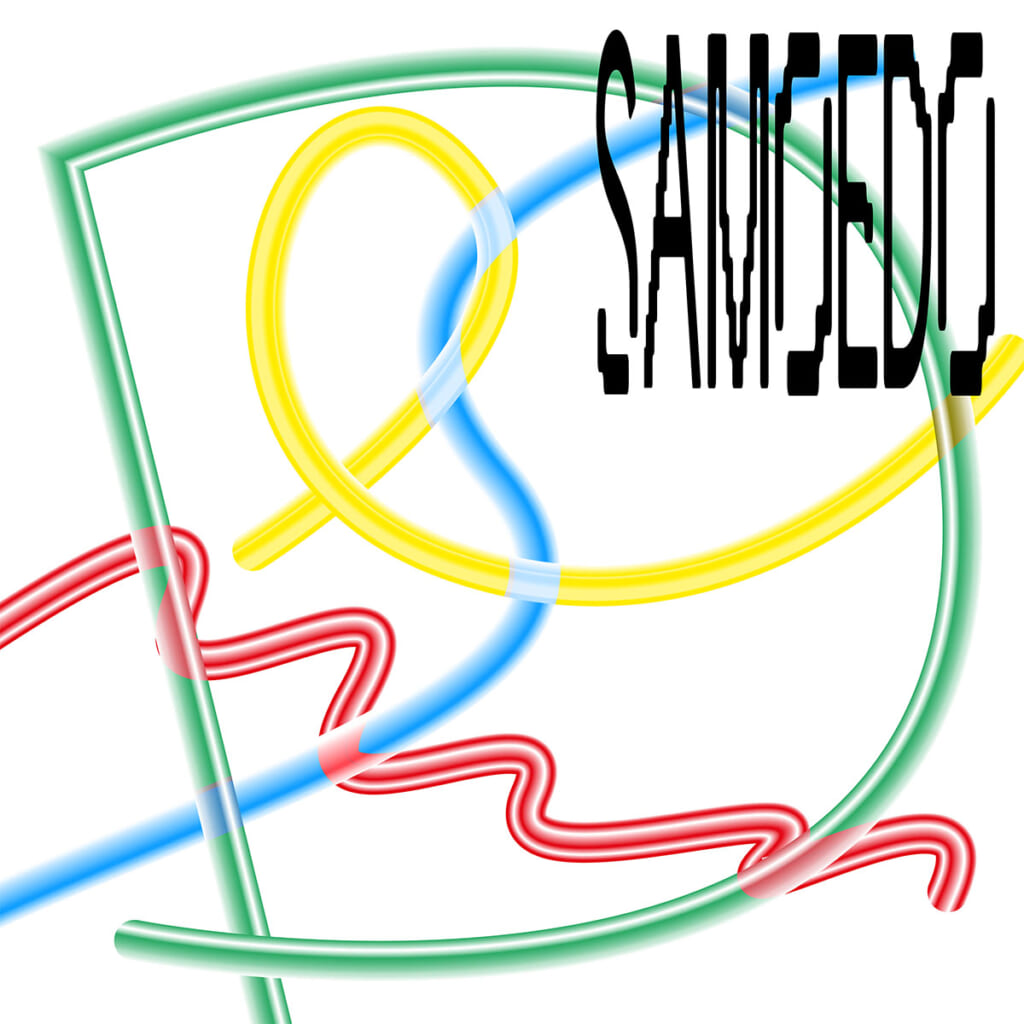シャムキャッツの解散後、アジアのポップ・カルチャー研究や書籍『アジア都市音楽ディスクガイド』の執筆、映画の主題歌や劇伴音楽の制作、バンドのプロデュースなど、多岐にわたる仕事を手がけてきた菅原慎一(Shin)。その彼がいよいよ自身のバンド=SAMOEDOを結成し、セルフ・タイトルの1stアルバム『SAMOEDO』をリリースした。しかし、本作では“「アジア」など、特定のイメージを想起させたくなかった”という。確かに、強い感情をも表現できるギターという楽器の鳴らし方にも“抑制されたクールさ”を感じる。今、菅原にとって、SAMOEDOをやることとは、ギターを弾くとはどういうことなのか? 本作を軸に紐解いていこう。
文=辻昌志 写真=Reina Tokonami

“菅原だからアジア”ってイメージからはうまく身をかわしながらやる
バンド結成にあたり、最初に想い描いていたサウンドはあったのでしょうか?
“都市のアート・ポリフォニー”と言ってるんですけど、シティ・ミュージックというのはわりと意識しましたね。
それは単に“都会で聴くのにちょうどいい音楽”、ということではなく?
そうですね。都市というのはシンプルに都会を指しているというより、色んな人間がいて、多様性がある場所っていう意味で。僕、そういうのがクロスオーバーしてワーッてなっているところが好きなんですよ。だからそんな場所で流れていて、何となくみんなが体を預けられる音楽っていうのが理想だなと。
資料にある“世界中のマクドナルドで流れる音楽を目指す”って表現は、聴くと凄くわかる気がしました。ヘッドホンで聴くというよりは、ちょっと遠くから流れてくるくらいの距離感が心地良いというか。
まさにそうで、スマホで何となく聴くっていうことでもいいと思うし、サウンドの方向性としては、あらゆる地域性などを無視したものというか。
資料のSAMOEDOの紹介文で、“90’sアジアン・ポップ・ムード”という言葉も見かけたのですが、地域性を考えないということは、菅原さんの中で“アジア”ですら、そこまで意識していないということ?
そうですね。全体を通して、なるべく特定のイメージを想起させたくなかった。自分の場合だと、1つはシャムキャッツをやっていたイメージもあると思いますが、その“アジア”も大きかったんです。なので、“菅原がバンドを始めたんだから、アジアでしょ”みたいなことからは、うまく身をかわしながらやるというか。
“菅原さん=アジア音楽”というイメージは正直強くなっていました。
そのアジア音楽ってなると、どうしてもワールド・ミュージックの文脈だけで語られることが多くて。ギター・マガジンでもアジアのシティ・ポップ特集(2020年1月号)で選盤と解説をさせてもらいましたが、そこで取り上げたように、地域性を超えたうえで良いって思えるギターを弾く人がたくさんいるんです。日本の音楽の影響を受けたからこそ彼らがいるっていう成り立ちではなく、ちゃんとそれぞれの地域に縦のラインで存在しているというか。
菅原さんが監修された『アジア都市音楽ディスクガイド』(DU BOOKS刊)にも詳しいですが、70年代に生まれたシティ・ミュージックは日本固有のものじゃなく、当時からアジア各国で都市音楽を追求する動きがあったわけですよね。
そうですね。本を作ったのは、自分がそれを“日本の世の中に伝えなきゃ”っていう、謎の使命感に襲われたこともあって(笑)。でも、その制作がほぼ終わりかけた時に、“あれ? 自分はどういう立場でこれをやってるのかな?”って思ったんですよ。あくまでも自分は日本人であって、ある種のエキゾチシズムやオリエンタリズム的な目線が入ってるんじゃないか?と、自問自答する時期がありました。
紹介する側という立場にいる以上、その目線を持っている自分から逃がれることは難しいと。
そこで一度立ち止まった時に、自分がこれまでにアジアで出会ったバンドやファンとの距離をもっと縮めたいし、同じステージに立ちたいと思ったんですよね。その方法っていうのが、彼らの音楽を日本で紹介することではなく、自分も同じようにバンドをやって表現することなんじゃないかっていう、めっちゃ普通のことなんですけど……。そこから、“じゃあ、どういうサウンドを鳴らそうか?”と構想を立て、コンセプトから作っていった感じですね。
それが“あらゆる地域性の無視”というサウンドの方向性にもつながっていくわけですね。
そうですね。確かにアジア感はあるかもしれないのですが、もっと広く、現代の音楽として普通に聴かれてほしいという願いはあります。
「Suiteki」のソロは、雨が降った日に部屋で録ったんですよ
今作では、シンセサイザーの音が曲全体の雰囲気作りに大きな役割を果たしていますね。ギターはそれに絡みついていくようなプレイだと感じました。
デモの段階では、僕は複雑なシンセのフレーズを入れられないし、歌とベースと、ちょっとだけギターが決まった段階で、鍵盤の沼澤(成毅)君に渡していたんですよ。そうすると、彼から返ってくるんですね。そこに少し辻褄を合わせるようなギターを入れたりはしています。なので、シンセとギターの両方が活きるようなリフが要所要所に入ってるかもしれません。ただ、実は自分もシンセを演奏していて。最近買ったんですが、“プチュー”っていうモジュラー・シンセの音は僕の演奏です。
シンセを自分で使ってみて、ギターに対する考え方で変わってくるものはありました?
ギターでも頑張ってシンセ的な効果を出すことはできるけど、そこは棲み分けだなと。“ギターにはギターの仕事がある”っていうか。何なんだろうな、ギター(笑)。常にグラビティを感じるというか、ネックに重力がかかっていて、持ち上げて動かせる感じとか……やっぱ面白いですよね。ダンスに直結してる気がします。
僕も実際「Suiteki」を聴いた時、小刻みに揺れるように体を動かしてしまいました(笑)。
あ、本当ですか? 嬉しい(笑)。ともかく、ギターってけっこう特殊な楽器だなと、改めて思ったんですよ。良くも悪くも、楽曲をギターのものにしてしまう。だから鍵盤奏者とバンドをやる時、そこは考えないといけない課題でしたね。
これまで、アンサンブルの中に鍵盤が入ることはあまりなかったんですか?
全然ですね。ギター・アンサンブルができあがっている中に、サポートであとから入ってもらうことはありましたけど、今はメンバーにいるからまた違う話になってくる。和音を積み過ぎちゃうと、聴いてる人の心地良さも変わってくるじゃないですか。そういう音楽も個人的には好きですが、例えばキーボードが4音鳴らしてる時は、自分がこれ以上音を入れるのはやめようとか。そういうことを凄く考えました。ただ、和音やハーモニーに関しては、沼澤君とnakayaan(b)が今まで培ってきたアプローチを最大限尊重してやってるので、着地点はあまり明確にしてなかったですね。というより、それを楽しみながらやっていたのかもしれません。
バンドならではの楽しみですね。“これ以上音を入れない”とは逆に、ギターの音を抜いていく、ということもあったんですか? ダンサブルなナンバーだと、ずっとギターを鳴らしていても違和感がない曲もあるように思えましたが。
そうですね。例えば「Dance Today」の最後にカッティングが入ってるんですけど、あれは最初、全編に入れていたんですよ。でも、これだと普通のバンドになっちゃうと思って。本当はいっぱい弾きたいけど、“最後のセクションだけに取っておこう”って残しました。けっこう我慢をしてますね。
最後に少しだけ現われるのもまたクールだなと。一方でギタリスト的なところで言うと……。
リード曲の「Suiteki」に数小節だけギター・ソロが入るんですけど、そこで……(笑)。
そこはまさに唯一、ピッキングのニュアンスから感情を感じました(笑)。ボリューム奏法的なこともやっていますね。
ですね。右手でボリュームをいじりつつ、フランジャーと組み合わせて音を出しました。
ソロといっても主張しすぎない、絶妙な温度感です。
あれ、いいですよね。スタジオに併設されているコテージの部屋で録ったんですよ、雨が降った日に。
なるほど。なおさら情景が浮かんできます。ギターは基本、マイク録りですか?
そうですね。ラインもありますが、基本は59年モデルのフェンダー製BASSMANからリボン・マイクで拾ってます。
“古いフィルムのような”……とか、そういう自分のイメージの逆を行きたかった
あと、菅原さんはもともと、空間系のエフェクトにこだわりがあったと思います。ですが今回はリバーブがかなり薄めですよね。これって逆に深くかけると、わかりやすくノスタルジックな雰囲気が出てしまって、それこそ特定のイメージにすぐさま回収されてしまうからなんじゃないかなぁと。
嬉しいですね、まさにそうです。
では意図的に薄めにしている?
そのとおりです。僕はずっとLine 6のDL4などを使ってたんですけど、今回はそれを禁じました。空間系で唯一使ったのはRolandのRE-201だけで、しかもたまに入れるくらい。あとにかかっているのは、ミックスの段階で韓国のエンジニアが乗せたものです。だからレコーディングの段階では、ほぼ空間系なしでやってるし、それは自分に課していたものでもあって。まさに今言われたように、自分のイメージみたいなものに対して逆を行きたかった。“ノスタルジー”、“日常的な”、“古いフィルムのような”……とか、よく言われるんですけど、もうそれら全部の逆を行きたくて(笑)。
そうでしたか(笑)。禁じることで、新たな一面が開花していますよね。歪みはペダルで作ったのでしょうか?
もう僕の一生物となるであろうTS9がメインです。とあるギタリストの方から譲り受けたものなんですが、中のチップの違いか、あきらかにオンリー・ワンな音がするんです。このTS9がなきゃ生きていけません(笑)。あとはDanelectroのFAB TONEと、昔アメリカに行った時に買ったDeath By AudioのINTERSTELLAR OVERDRIVER。その3つかな。
ギターは何を?
ずっと使い続けているアメリカン・ビンテージ・シリーズのストラトキャスターです。2012年製だから、ちょうど10年か。

メイン器として長くなってきましたよね。
面白いのは、ここにきて自分の体の一部と感じるくらい、相棒感が増してきたんですよ。そのストラトは楽器屋さんに通い続けて、何十本も見せてもらった末に選んだ1本で。一番自分に合うものを買ったわけなんですが、もう僕の体も一緒に成長してきた感じというか。実際、コンターが体に当たる部分も……。
そこがストラトに合わせて変わってきた(笑)。
(笑)。塗装がめちゃくちゃ薄いのですが、それも剥げてきていて。本当に凄くカッコいいんですよね。今回、新しいバンドを始めるから機材もガラッと変えようとも思ったんですけど、“まだまだコイツで色んな表現ができるな”と。ギター側でちょっとトーンを絞るとか、各曲でやったりしてますね。ただあと1本だけ、実はカジノを使っていて。
新たに買ったんですか?
弟がくれたんですよ。実家に戻った時に“こんなの持ってんの? レコーディングで使うから貸してくれない?”って言ったら、“じゃあ、あげるよ”って(笑)。
気前が良いですね(笑)。
「Goodbye de」のアウトロでポリリズムみたいなことをやってるんですけど、その箇所で。カジノ、チープで良い音がするんですよ。
さて、8月10日には今作のリリース・パーティーを控えていますね。ライブに向けて、バンドはどんな状態ですか?
今、ライブ用にアレンジをしてるんですけど、アルバムが8曲で23分しかないんですよ。ヤベえなって、今ちょっとリアレンジをしてるところで(笑)。
(笑)。1曲10分くらいやってもよさそうな曲も多いですよね。
確かにそうですね。曲によっては、ミニマムなビートを反復させて、長くしてもよかったなって曲も全然あったんです。でもそこは、パッケージされた時のことを考えながら作りました。レコードにした時、この長さだとギリギリ回転数を45回転にできるっていうのと、今はデジタルで聴ける時代だから、スマホでパッパッと聴いたとしても刺さるようにしたかった。それで結果的に短くなりました。でも、ライブでは長くやりたいですね。聴いている人を逃げられないようにして(笑)。
すでに新曲も作っているんですか?
そうですね。nakayaanもデモをめっちゃ送ってきてくれるんです。アイディアは常に湧き出ている状態なので、それをいかにまとめあげるかが次の楽しみであり、課題ですかね。クリエイティブな制作をして、いいギターを弾いて、そして世界中でライブをしていきたいです。