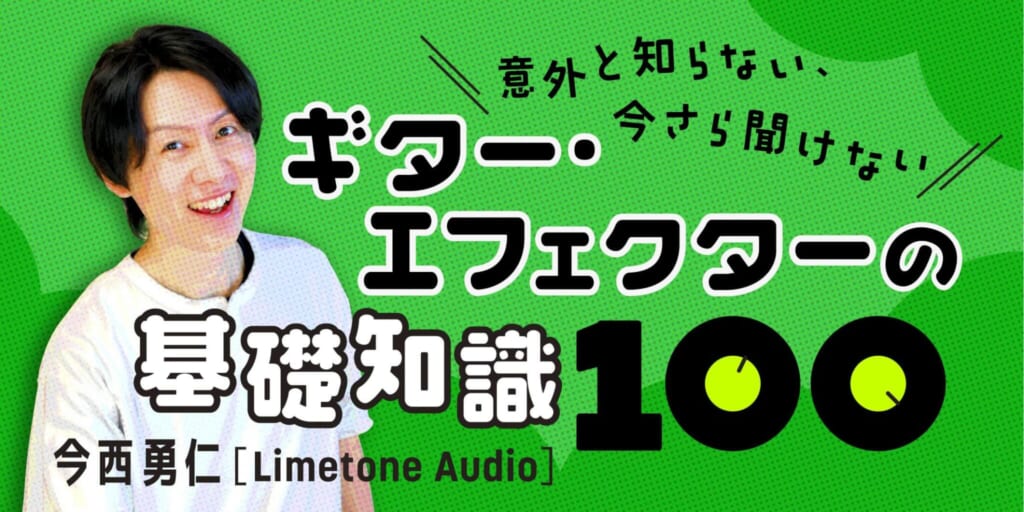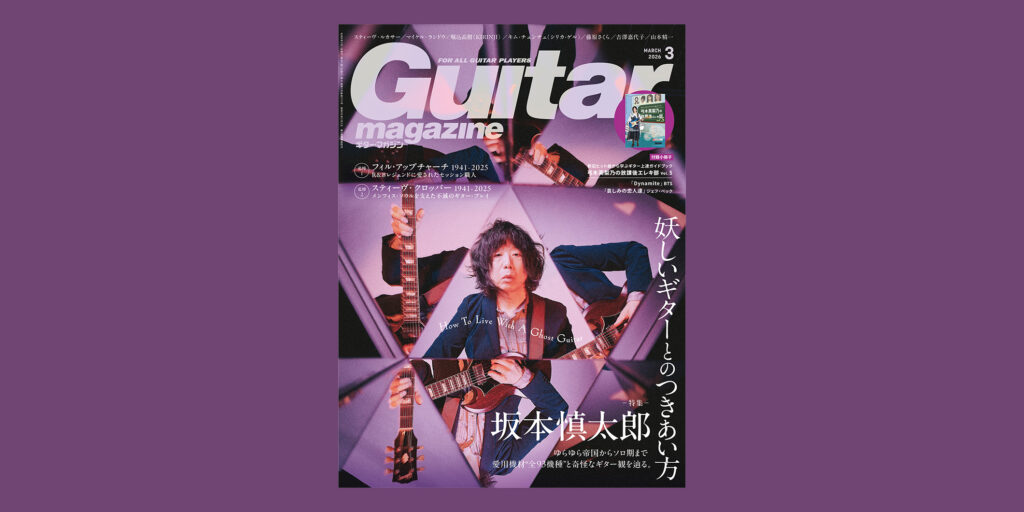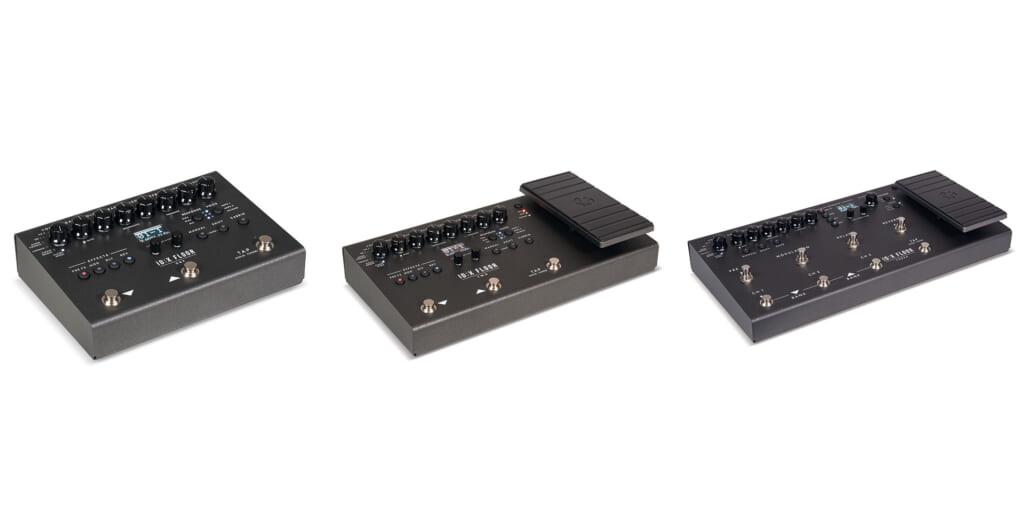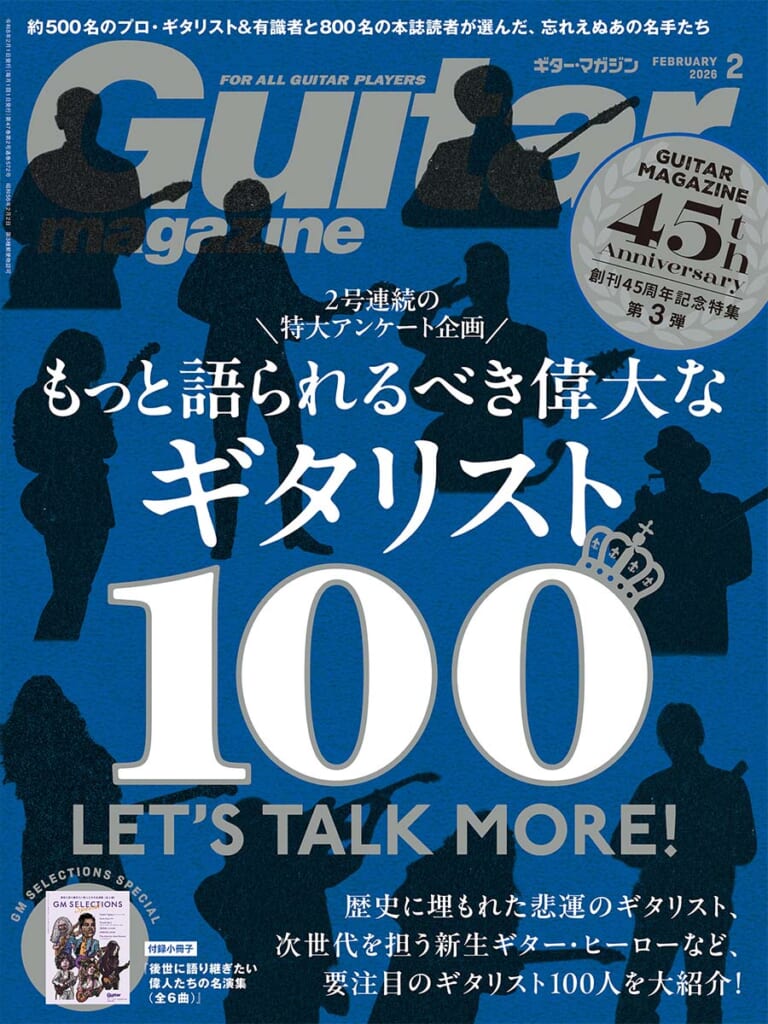元ねごとのマスダミズキのソロ・プロジェクト“miida”が満を持して発表した初のフル・アルバム『miida』。本作には、これまでマスダが吸収してきた幅広い音楽性のみならず、音楽家としての新たな挑戦を感じさせる点が多くある。ドリーム・ポップ・チューン「bergamot memories」でのオルタナ/ガレージ的なギター、「Rain」で聴けるダンサブルなカッティングに加え、オカモトコウキ(g)のソロで彩られた「melt night」のレイドバックしたグルーヴは新鮮だ。こうしたギターのアプローチについては“自分の中から自然に出てきたもの”だという。そんな彼女に、新作の制作について語ってもらった。
取材:錦織文子 撮影:藤岡柊平
できることから始めて
自分の力でやっていかなきゃと
思い立ったんです。
ソロ・プロジェクトとして初のフル・アルバム『miida』の発売、おめでとうございます!
ありがとうございます!
2019年のねごと解散後、すぐにmiidaとしての活動を始めて、現在に至るまでに色々なことがあったかと思います。まずはプロジェクトを始めた時の話から聞かせて下さい。
バンド解散前から4人はバラバラになってそれぞれの活動をしていくとはわかってたんですけど、私は1人でも音楽は続けていきたいという思いはあったんです。なんとなくそう思っていたところに、当時のマネージャーさんがバンドの最後のツアーが始まる前に“何か次にやることの告知があるならフライヤーにして折り込むよ”と言ってくれたんです。“それなら……”と思って、そこで新しいプロジェクトの告知をしたんです。
図らずもそれが後押しになったという。
そうですね。何気ない一言だったと思うんですけど、そこからスタートを切ることになって、早速ライブの準備や曲作りを始めていきました。最初はドラムのsugawaraさんと一緒にやっていて、2020年に1stミニ・アルバム『utopia』も出したんですけど、ちょうどその頃にコロナが本格化し始めて、sugawaraさんが脱退して1人になって。レコーディング・スタジオもライブハウスも休業になってしまったし、1人でも制作できる環境を作らなきゃと思ったんです。それで家に防音室を運び込んだり、防音機材を揃えたりして、現在のStudio KiKiができたんです。
凄い行動力ですね。
もちろん最初はできないこともたくさんあったんですけど、できることから地道に始めて、自分の力でやっていかないといけないなって思い立ったんです。1ブースあれば、基本的にはどのパートも録れるので。
ソロとしてのmiidaになり、プロジェクトの音楽性に変化はありましたか?
当初はsugawaraさんと2人でやりたいことを提案し合って作ってきたので、彼が抜けてしまって白紙に戻ったんです。そうなった時に、“あれ、どうしようかな? やろうと思えば何でもできちゃうけど、自分は何を選ぶべきなんだろう?”って一旦放り出された感じがあって。だから1人になってからすぐは、あまり曲作りに本腰を入れられず、ミニ・アルバム発表の準備をしたり制作環境を整えたりして、今回のアルバム制作に着手していった感じでした。
前作『utopia』でのギターはオルタナティブ/ガレージのテイストが色濃かったと思いますが、新作『miida』はまたガラッと変わった印象があり、ダンスやヒップホップ、R&B、ネオソウルなど幅広い音楽性を感じました。作風の方向性はあらかじめ決めて制作に挑んだのですか?
最初から具体的な音楽性を決めていたわけではなくて、ギターをいじってみたり、PCでビートを作ってみたりとやっているうちに、自然と今の形になっていきましたね。オケを作っているうちに、自分の好きなものが自然と入っていったという感じです。
オケを作る時はどのパートから組んでいくんですか?
初めは必ずドラムからですね。
ドラムから! それは予想外でした。
最初にリズム・セクションを作る時にお気に入りのビートを作って、そこに感じた音楽に寄せていく流れで作っていますね。バンドにいた頃から作曲する時はいつもそうなんですよ。ギタリストだから弾き語りから始まるんじゃないかと思われそうですけど……ギターからはなかなか作りづらいんですよね(笑)。今作も弾き語りで作ったのは「Lucky」だけで、それも珍しいんです。だから、レイヤーの重ね順としては、ドラム、コード、ベース、ギター、そして最後に歌という流れです。
好みのビートを作る時は、どんな音楽から影響を受けていますか?
ヒップホップやR&Bで聴けるようなビートが好きですね。パッと思いつくものだとDr.ドレーとか。
たしかに「Trash into The Sea」などは、90年代ヒップホップの印象も感じました。
ビートについては、まさにそうですね。
ねごとでのミズキさんのプレイに感じる音楽志向とは違って、そういった音楽ジャンルが一番に出てくるというのは意外でした。
バンドをやり始めた頃はインディー系のオルタナが好きだったんですよ。それからテクノが好きになってからビートへの興味が湧いてきて、実際に作曲時のドラム・アレンジにも取り込むようになったんです。それからヒップホップやR&Bも聴き始めるようになって。だからここ数年で聴いているものの影響はありますね。
曲を彩る要素として
ギターを聴かせる
昔からそのほうが得意なのかな

新作はビートやシンセなどによって全体的にエレクトロ寄りの曲調が多いですが、そこでギターがうまく馴染んでいる印象がありました。フレーズ作りはどのように?
ギターはバッキング要素というよりは、上物として入れることが大半ですね。基本的に曲作りにおいては中域にシンセが入っていて、ギターでは何をやってもいいという自由さがあるので、曲を彩る要素として聴かせること多いです。単純に昔からそういうアプローチが得意なのかな。
最近のエレクトロ系の楽曲だと、ギターが聴こえるとしてもバッキングがうっすら入っている程度のものも多いと思うんです。今の音楽として聴かせつつ、そこにギターの存在感もいい塩梅で出しているのが新鮮だと思いました。
そう言ってもらえて嬉しいです! 意図的にそうしようと思っていたわけではないんですけど、ねごとではさっちゃん(蒼山幸子/vo, key)が鍵盤でコードを弾いていたので、ギターでは上物として立ち回るほうが自分の中にイメージしているものをナチュラルに表現できるんです。
今作のギターはオカモトコウキさんとミズキさんでレコーディングされたそうですが、コウキさんが参加することになった経緯は?
ある日突然コウキ君が、“俺、弾こうかな〜”って言い始めたんですよね(笑)。1人でやるつもりだったので最初はびっくりしたんですけど、“やってくれるなら弾いてもらおうかな”と思って。オケの段階でアレンジまで完成していたので、個人的に早く仕上げたいものは私が弾いたものをそのまま使ってミックスして、“コウキ君が弾いたらどうなるんだろう?”というフレーズは弾いてもらいましたね。
一緒にレコーディングしてみて、どうでしたか?
やっぱり手癖、ノリ、ピッキングの強さも私とは全然違うので、弾きづらそうなものもあって。例えば「fade out」はもともとオケで入れいていた私のバッキングのノリと、コウキ君の手癖がかなり違っていて、結局自分の思い描いたノリには近づかなくて、申し訳なさはありつつも自分の弾いたフレーズのままミックスしました(笑)。簡単そうなフレーズでも、こんなに違いがあるものなんだという驚きもありましたね。時間はかかりましたけど、レコーディングの間のやりとりで生まれたギター・フレーズもあって、新作のソロに関してはすべてコウキ君が弾いてくれたものですし、本当に大収穫でした。
ギター・ソロと言えば、「melt night」のメロウなプレイは曲の雰囲気を見事にまとめ上げていて素晴らしいです。
いいですよね、この曲をうまく彩ってくれました。これは2回くらい弾いてすぐ決まりました。レコーディングに参加してくれたベースのアベ(マコト)君もその場にいて、みんなで“めっちゃいいね〜”ってなって。ソロだけど、そんなに歪んでない感じもいいんですよね。
この曲だけほかの収録曲とはまた雰囲気が違っていて、それこそテープ・エコーを使ってもいますが、曲作りはどのように?
高校生の時から大好きだったフィッシュマンズにインスピレーションを受け作りましたね。あそこまでオーガニックなサウンドではないですけど、レゲエっぽいノリは意識しました。テープ・エコーはECHOPLEXが家にあったので、この曲で使うしかないと思って、ギターのバッキングにはずっとかけていますね。
ほかにもコウキさんらしさのあるロックなリフが聴ける「Continue」も印象的でした。
一番最初のバージョンで私が弾いたバージョンをコウキ君にアレンジをしてもらって、そこからコウキ君にまた弾き直してもらい、最終的にミックスして試行錯誤を重ねましたね。もちろんロックなテイストは出したいと思ってお願いしたんですけど、コウキ君が弾くとこんなに色濃くなるんだとびっくりしました(笑)。ちょっとブルージィな感じもあって。それも彼のアレンジの癖が出ているんだなと思います。オケを作った当初はマイナー・キーのコードをこんなにたくさん使ってなかったんですよ。
歌や楽曲全体のテンション感に合わせているようにも聴こえます。
それは考えてやってくれたかもしれないです! それと、この曲はドラムの質感もわざとらしくしようと思ったんです。最近だと、The 1975とかがミニマムな上物に対してドラムのバック・ビートにリバーブが大袈裟にかかった80’sっぽい印象があって。ああいう違和感にヒントをもらって、スタイリッシュになりすぎないで、耳を惹くぎこちなさを出したかったというか。
そうすることで、逆にギターの輪郭が引き立つ。
そうなんです。自分が曲を作るならやってみたいと以前から構想していて。で、この曲はギターがいなたくなってしまいそうだったので、そこに相反するヘンなドラムを入れたら、不思議な質感になるかなって。そのアンバランス感は上手く出せたんじゃないかな。
自分で可能性を広げて
色んなつながりができて
今がすごく楽しい
「bergamot memories」はパンチの強いビートと野太いベースラインによってダンス・ポップ。曲のブリッジ部分でのオルタナ的な歪んだギターにミズキさんらしさがあるなと思いました。
これは本来の自分のルーツが出ているかもしれないですね。ドリーム・ポップっぽいサビに入っていく感じをやりたくて。2010年代の半ばあたりはチルウェイブみたいなのが流行りましたけど、ああいうのが凄く好きで。そこにグランジやオルタナの要素が合わさったらいいなと思い描いているうちにできあがりました。歪んでいるフレーズでは、BOSSのBD-2とビッグマフを使っていますね。
ちなみに、次曲「Color」で入ってくるディストーションの効いたバッキングはミズキさんが弾いたもの?
これ、実はシンセでやったフレーズなんですよ。“この音色、めっちゃギターっぽい!”って思って入れました。
え! それはまったく気づきませんでした……。あえてシンセでやったのはなぜですか?
曲の質感に馴染むようにするなら、シンセのほうがいいなって思って。オクターブ・ファズをかけているようにも聴こえる少し違和感のあるサウンドなんですが、その無機質さがぴったりだなって思ったんです。ギターっぽいフレーズにこだわったのは、自然な発想でしたね。
改めて、これまでのmiidaとしての活動を振り返ってみてどうですか?
ソロ活動を始めてから、思いがけずギターのお仕事をいただくことが多くなって。まさかRADWIMPSでアリーナ・クラスの会場で演奏するとは思っていなかったですし、そういう意味では音楽との関わり方がバンド時代とはまた違ってきている感じもあります。“私って、ギタリストなんだな”って、最近気づきました(笑)。
バンドの“ギター担当”ではなく、1人のギタリストだと。
ギタリストとしてのキャリアでやっていく選択肢も自分にあったというのが、ちょっと意外でしたね。バンドに所属して活動することの楽しみももちろんあると思うんですけど、今こうして自分で可能性を広げていっていますが、その中で色んなプロジェクトに呼んでもらって、つながりが増えて……今が凄く楽しいんです。そうして音楽で私と関わってくれるすべての人たちに感謝したいですね。
“ギターは曲を彩るもの”という話が先ほどありましたが、ギタリストとしてのプライドを感じました。
嬉しいです。今後も頑張ります!
最後に、今後の制作活動の展望を聞かせて下さい。
ギターのお仕事に呼んでもらう機会が増えて、ギターを毎日触るようになり、“あ、今ギター凄く楽しいかも”っていう時期になっています。なので、次はギターから曲を作ることにもチャレンジしたいですね。

作品データ

『miida』
miida
miida/MCD-02012/2022年8月24日リリース
―Track List―
1. Rain
2. bergamot memories
3. Color
4. melt night
5. swim in boredom
6. YOU
7. Continue
8. Trash into The Sea
9. (I don’t wanna) fade out
10. be true?
11. LUCKY
12. utopia(The Department Remix)
―Guitarists―
マスダミズキ、オカモトコウキ