LOVE PSYCHEDELICOのKUMI(vo,g)、深沼元昭(PLAGUES/Mellowhead:g)、 林幸治(TRICERATOPS:b)、岩中英明(d)によって結成された新バンド、Uniolla(ユニオラ)。彼らが1st作となるセルフ・タイトル・アルバムを完成させた。伸びやかで美しいKUMIの歌声と、それを彩るイギリスのネオ・アコースティックのような憂いを帯びたアンサンブルが心地良く鳴り響く作品に仕上がっている。バンド結成の経緯やアルバム制作について、KUMIと深沼元昭に話を聞いた。
取材=尾藤雅哉(SOW SWEET PUBLISHING)

ただ素直に歌ってみたら
マジックが起きた(KUMI)
まずはUniollaというバンド結成の経緯からお話を聞かせて下さい。
深沼元昭 もともと、僕のソロ・プロジェクトであるMellowheadで、“KUMI from LOVE PSYCHEDELICO”みたいな形で何曲か一緒にやろうと思って。最初に3曲ほどデモを作ったんですけど……実際にKUMIが歌ったものを聴いたら“どうも違うな”と。KUMIのボーカルに一番ふさわしい楽曲を作っていたはずなんですけど、彼女の歌が入った瞬間に、全然得体の知れない別の表現になったと感じたんですよね。そこで“これはバンドで表現するべき音楽なんじゃないのかな?”という考えになり、仲の良い林(幸治/トライセラトップス)君とヒデ(岩中英明)君に声をかけたのが始まりです。
KUMI 本当に不思議だったね。NAOKIと2人でやってるLOVE PSYCHEDELICOは、バンドではあるんだけれども2人っていう人数的な制限もあって……自分たちで自分たちの楽曲を再現し切れないという意味では、ある意味“バンドには届かないジレンマ”もあったりしたんですよ。いつでもメンバーが集まってライブができる、みたいなフットワークの軽さはないっていうか。だから“いつかバンドをやってみたいな”っていう漠然とした“憧れ”は、自分の中にずっとあったんです。
深沼さんから一緒にバンドをやろうと誘われた時の気持ちは?
KUMI もともとMellowheadが大好きで。彼の書く曲の世界観や歌詞が好きだったんですよ。なのでバンドに誘ってもらった時は“一緒に音楽を作れたら面白いな”と思いましたね。私にとって、自分で制作してない曲を歌うっていうのは初めての経験だし、どんな表現になるか自分でもわからなかったけど、まずは1曲チャレンジしてみたい!というところからスタートしたんです。
で、最初に聞かせてもらったデモが3曲ほどあったんですけど、どれも素敵だったから、試しに全部歌ってみたんですよ。その時は、“LOVE PSYCHEDELICOとは違う風に歌おう”とか“日本語が多いからこんな声色にしよう”なんてことはまったく考えず、ただ素直に歌ったんですけど、そこでマジックが起きた。Mellowhead+KUMIじゃなくて、なんか1つのバンドの中のキャラクターがフッと立体的になった気がして。それを自分で客観的に聴いて、“これは確実に何かが起こってるから、1回だけの企画ではなくてバンドじゃないかな?”って。
深沼 改めて今考えてみると、ここに入ってる曲がMellowhead featuring KUMIだと、みんなピンと来ないもんね?
KUMI うん。Mellowheadとも、またちょっと違うよね。
深沼 そうだね。Mellowheadはわりとサウンドプロダクト的に凝った曲が多いんですけど、それをやってしまうと、どう考えても蛇足になってしまう気がしたんですよね。表現を“無理やり変えているに過ぎないな”と思ったから、これはもうバンドという形でやろうと。
UniollaでのKUMIさんの歌声は“軽やか”な印象を受けました。LOVE PSYCHEDELICOだと、もうちょっとブルーな部分を感じるというか。
KUMI そうですね。Uniollaだとマイナー調な曲がほとんどないし……。知り合いからは、“笑ってるように歌ってるね”って言われたり。“明るい”とか“軽い”とか。自分でも“そうだな”って思う。
楽曲を聴いた時、ペイル・ファウンテンズのようなネオアコ的な雰囲気を感じました。ちょっと憂いがありつつ、ポップなメロディやアンサンブルの中に攻撃性を潜ませている、みたいな。
深沼 そうそう、ペイル・ファウンテンズは制作の時にちょっと聴き直したりしていましたね。僕の場合、デビューがPLAGUESだったから、こういった方面の自分のルーツってあまり知られてなかったんだけど、自分の年齢的にはどうしても通るというか……アイディアと精神性の部分に対する熱さみたいな部分は自分の表現の中で血肉になっている部分ですね。ソフト・サウンディングなんだけど、ものすごい熱さがある、みたいな。
KUMI そういうバンド像っていうのは、途中から出てきたよね。
ギターもコードで壁を作るというよりはシンプルな単音フレーズで構築していくアプローチですね。
深沼 イメージしたのは、竹林みたいなアンサンブル(笑)。隙間だらけなんだけど、その隙間があるからこそアートになっている、みたいな感じなんです。入れようと思ったらあと2~3本くらいギターを重ねられるんだけど、あえて入れないっていうところでバンドとしての魅力が伝わればいいなって気持ちがありましたね。
「A perfect day」や「無重力」を始め、2人で弾く単音リフは1つのキーポイントのように感じました。コードとフレーズのように役割を分けるのではなく、同じフレーズをダブリングすることで旋律の強度が強くなり、聴き手の耳に残るというか。
深沼 「A perfect day」のマンドリンは、僕とKUMIの2人で同じことをやってるんです。これはレコーディング・エンジニアをやってくれたNAOKI(LOVE PSYCHEDELICO)君の提案なんですけど、“どっちから録る?”、“ブースどうする?”って尋ねたら“いや、1つのブースに2人で同時に入って弾こう”って(笑)。それを2本のマイクで録ってるんですよ。わざわざ混ぜて。
どちらのマイクにも相手の音のかぶりがある、と。
深沼 そうそう。その“音がかぶった状態”を録りたいというNAOKI君のアイディアだったんですよね。彼の、音を録るということだけではない“場をとらえるうまさ”みたいなものは、すごく今作に収録された弦楽器には大きな影響があると思う。
KUMI そうだね。その場の空気感ごと大事にするみたいな。
深沼 やっぱり“音が混ざった空気”っていうのは、その時しか録れないからね。
先ほど深沼さんからは“竹林のようなアンサンブル”というキーワードもありましたが、KUMIさんはギターを弾く上で深沼さんとはどのような話をしたのですか?
KUMI そんなに細かい話はしなかった気がする。深沼君も、私が弾くことをイメージしてフレーズを考えてくれているから、私が自然に弾けるギターになっているんだけど……そういえば私がメインで弾くギター・リフの音を表現する時、いつも“トテトテ”っていう言い方をしてたね(笑)。
深沼 “トテー、トテーってやって”っていう(笑)。
KUMI そのトテトテっていう表現は共通言語だった。文字では伝わりにくいけど、淡々と弾くというか、一生懸命弾かないというか、抑揚を出さないというか。
深沼 同じフレーズでも、僕がその“トテー、トテー”って感じを表現しようとすると、全然違うものになってしまう。
KUMI もちろんギタリストだから弾けるんだけれども、私の場合は、一生懸命やってあのたどたどしい感じの“トテトテ”だから(笑)。
深沼 そういうシンプルなフレーズなんかも、僕が弾くと“あえてやってんだぜ”みたいな変なスケベ心とかいろんな思いが交錯してしまうので(笑)、KUMIにも弾いてもらったりして。やっぱり彼女が無心で弾いたリフには絶対敵わないんですよ。
レコーディングでは何度かテイクを重ねたりしたんですか?
深沼 重ねる暇がなかった(笑)。時間をたっぷり使って音作りはするんだけど……録る音が固まった頃には演奏する時間がないんだよな、もう(笑)。
KUMI NAOKIの音作りに対するこだわりがすごいから。
深沼 バスドラの音を作る間に、たぶん10テイクくらいやれたと思う(笑)。
KUMI 待っている間にみんな疲れちゃって。録音できる環境が整った頃には“もう1~2回でやろう”っていう(笑)。
ギターにはそれぞれ個性があって
それぞれの“不自由さ”が
面白い楽器だと思う(深沼)
「どうしても」のイントロは、ザ・ドアーズの「ハートに火をつけて」のオマージュのようなフレーズで、個人的にグッと心をつかまれました(笑)。
KUMI あのオルガンが良いよね。
深沼 この曲はオルガンが主役なので、“エレキ・ギターの音は別に要らないかな”と思っていて。だから、中盤からガーンと入ってくるだけで、ほとんど入ってないんですよ。シュンちゃん(渡辺シュンスケ)がファルフィッサで弾いてるんですけど、“オルガンが一番偉い”音作りにしました。包むような柔らかいオルガンは必要なかったので、遠慮なく前に出てきてほしかったんですよね。
ギターは僕とKUMIが弾いたアコギが2本と中盤あたりにエレキが入っているんですけど、「にぎやかしでやればいいかな」みたいな感じで、あんまり重要視してない(笑)。どちらかというとギターは背景を描くような役割でした。
「手探り」のバッキングは、個人的にクラビネットのようにも聴こえました。どのように弾いているんですか?
深沼 ちょっとクラビっぽく聴こえる感じのパートはリッケンバッカーですね。660というモデルなんですけど、ああいう音するんですよ。トム・ペティがジャケット(※79年発売の『破壊』)で12弦ギターを持っているんですけど、それの6弦バージョンですね。
なぜリッケンバッカーを使おうと思ったのですか?
深沼 やっぱり僕自身、自分が手にしているギターのイメージってゴールドトップのレス・ポールなんですよね。特に佐野元春さんのバンドで弾いている印象が強くて。なんだかんだでゴールドトップを持ってる写真ばっかりだし。なので、このバンドでは“脱レス・ポール”でいこうかなって思っていて、自分の得意なギターをあまり使ってないんですよ。“なるべく得意技を出せない状態で頑張ろう”みたいな感じでした。
あとレコーディングの後半に60年代後半製のグレッチのテネシアンを手に入れて。こないだやったスタジオ・ライブの時にも使ったんですけど、メインで使っていこうかなと思っています。
そういう縛りを自分に課した理由は?
深沼 やっぱり手癖防止になるのかな? なにか土壇場になった時に“いつものこれをやっておけばカッコいい”みたいなところに逃げないようしたというか。そうなっちゃうと、自分でも面白くないですからね。
KUMIさんは、深沼さんがこんなことを考えながら弾いていたことを知っていたんですか?
KUMI うん、知ってる(笑)。
深沼 例えば「A perfect day」のソロは、NAOKI君のテレキャスを借りて弾いたんですよ。その場でパッと渡されたギターで勝負するというか。
やっぱり手にするギターの種類によってフレーズも全然変わってきますよね。
深沼 そうなんですよ。そういう意味でも、今までの手癖から脱却したかったし……そういう縛りを作って弾くことで“知らず知らずのうちに、今まで開かなかった新しい引き出しが開かねえかな?”みたいなところでやっていましたね。なのでUniollaのライブでは、テネシアンをメイン・ギターにしようと思っているんですよ。レス・ポール的な常識が通用しないモデルを使うという(笑)。
ギターって楽器は、それぞれサステインの長さだったり、ハイポジションの弾きやすさだったり、いろんな個性があるじゃないですか? そういう“不自由さ”が面白い楽器だと思うんですよね。そのギターに合った弾き方だったり、手にしたからこそ生まれてきたフレーズはとても重要だと思う。
また「手探り」で聴ける感情をむき出しにしたようなソロは、アルバム全体として淡々としたプレイが多い分、すごく耳に残りました。
深沼 そうですね。今回のアルバムの中では“一番僕らしいギター・ソロかな”って感じがしますね。使ったギターは、ストラトです。これもルーレット方式というか、その場でたまたま手にしたギターで弾いたテイクですね。
KUMI 楽しんでるよね。
深沼 うん、楽しんでる(笑)。ただ、Uniollaの曲ってすごくシンプルだし、ミュージシャンがすごく自由に演奏できる余地がある。決まりごともすごく少ないし、“他の人がこれをやってるから、その音を避けて”とかもあんまりない。なので曲自体に、みんなが思う存分“暴れられる”余地があるんですよ。だからこそ自由に表現ができたって部分はあるかもしれない。
なるほど。ちなみにKUMIさんが使用したギターは?
KUMI 私が持っているエレキって(フェンダー)ジャガーとES-330くらいなんですよ。
深沼 でも、ビグスビーが付いているものすごい重いレス・ポールとかあるじゃん。
KUMI あ、レス・ポールも持ってるね。でもUniollaには“ジャガーが絶対合うだろうな”と思って。もうジャガー、一択でした。音作りに関しても、現場にギタリストが2人もいるから、もう全部お任せで(笑)。
深沼 僕とNAOKI君で、“これ60年代製の良いジャガーなんだよ”、“今買うとめっちゃ高えよ”とか言いながら勝手にやっちゃってね(笑)。
KUMI ね。良い音するのよ(笑)。
深沼 今回、バンドで使うにあたってもリペアに出したんで、すごく状態も良いんですよ。
KUMI そうそう。すごく弾きやすくて、弾いていて気持ちがいい。
エフェクティブなアプローチもあまり多くないですが、「No pain」のソロで聴けるファズ・サウンドも印象的でした。何を使ったんですか?
深沼 あれ、何でやったんだろう……たしかLine 6のM9じゃないかな? M9のチャンネルを2つ使って“ファズ×ファズ”で鳴らしていたと思います。僕、M9が大好きなんですよ。古いアンプと歪みサウンドの相性も不思議と良かったりしますし(笑)。超ショートリバーブの後段に歪みを入れて残響を歪ませてみたり……色んなエフェクトを組み合わせる実験ができるので面白いですね。Uniollaでは、バンドの世界観とかけ離れてしまうから、そういうアプローチはやっていないですけど。

“これから未来に向かっていこう”という
キラキラした希望が詰まっている
スペシャルな1stアルバム(KUMI)
改めて、KUMIさんから見た深沼さんはどんな音楽家ですか?
KUMI ギタリスト、コンポーザー、アレンジャー、プロデューサー……色んな顔があるから……。ちょっと待ってね、イメージしてみる。
深沼 身近にいる人がNAOKI君だからね。彼自体がめちゃくちゃ特殊だから(笑)。
KUMI うん。NAOKIもすごく変わった人だね(笑)。
深沼 僕もどちらかと言うとNAOKI君寄りなんですよ。録音もできて、わりと細かいことに強いギタリスト、みたいな。
KUMI そうかもね。あらゆる分野に長けてるからね。どんな人なのか、全貌をまだ知らないのかもしれない(笑)。曲書けて、あんなにいい詞も書けて……それで機械もいじれて。
深沼 機械ね(笑)。
KUMIさんは、そこはちょっと苦手な感じ?
KUMI うん。自分ではやらないから、そういう人が近くにいてくれて、すごいラッキーだと思う。
深沼 身近に2人もいるっていう。
KUMI しかもUniollaに関しては彼が曲も歌詞も全部作っているしね。そうやって音楽に関わることが基本的に何でもできて、そのすべてに情熱を注いで楽しんでやっている。だから一緒にやっていて楽しいし、どんなアイディアを投げても全部的確にとらえてくれる。“音楽”という目に見えないイメージを扱う中で、ちゃんと形にできるのがすごいことで、“こうなれたらいいよな”と思う1つの理想だね。
では深沼さんから見たKUMIさんの魅力とは?
深沼 KUMIは、表現に迷いがないんですよね。揺るぎない芯があるというか……例えばUniollaのアーティスト写真に書いてあるバンド名は、ミュージック・ビデオの撮影中にKUMIが書いたものなんですけど、あれは演奏シーンが終わって外に出てきて、そのまま一筆目にあれをズバッと書いたんです。普通、絶対にできないですよ、そんなこと(笑)。僕だったら悩みに悩んで、10テイクくらいやっちゃうと思う。だから彼女をみていると、もう自分のやっていることが正解かどうかなんてことを考えている時点で、もうダメなんだなって。
KUMI 見直して反省しないもんね(笑)。だって反省したら、“これ、ちょっと悪かったな”とかなるじゃない。
1stアルバムを作り終えて、これからライブも控えていますが、2人りはUniollaというバンドにどのような可能性を感じていますか?
KUMI もう余地だらけというか、“可能性だらけだな”って思う。これから書く曲にしてもバンドの在り方にしても縛られてるものが何もないから。
深沼 今作の曲もライブで演奏を重ねていくと成長していくだろうし、僕らも“この先どうなっていくのかな?”っていうのを楽しめる気持ちがあるからね。
KUMI 楽しむ気持ちが一番かもね。
深沼 すごい大きい。楽しんでる。
KUMI 楽しんでるっていうのが、一番の余地というか、可能性なのかもしれない。
深沼 そうだね。Uniollaをやれていることが“すごく幸運だし楽しいな”って思っています。
最後に作品制作を振り返って一言お願いします。
深沼 どれだけキャリアを積んでも、いくつになっても、“バンドって楽しい”、“演奏って楽しいな”って思えるような、ミュージシャンのプリミティブな部分がすごく出ているアルバムになったと思います。そういう意味でも、楽器を弾く人にこそ聴いてほしいって気持ちがすごくありますね。
KUMI Uniollaの曲を演奏するの、きっと楽しいよね(笑)。
深沼 楽しいと思う。曲も簡単だし。
KUMI 1stアルバムってスペシャルじゃない? そこにはUniollaが誕生してバンドになっていくワクワクした部分やピュアさ、“これから未来に向かっていこう!”というキラキラした希望が詰まっていると思うから、このアルバムの音と空気に触れてくれたみんなも一緒に、そういう気持ちになってくれたら嬉しいと思います。
作品データ
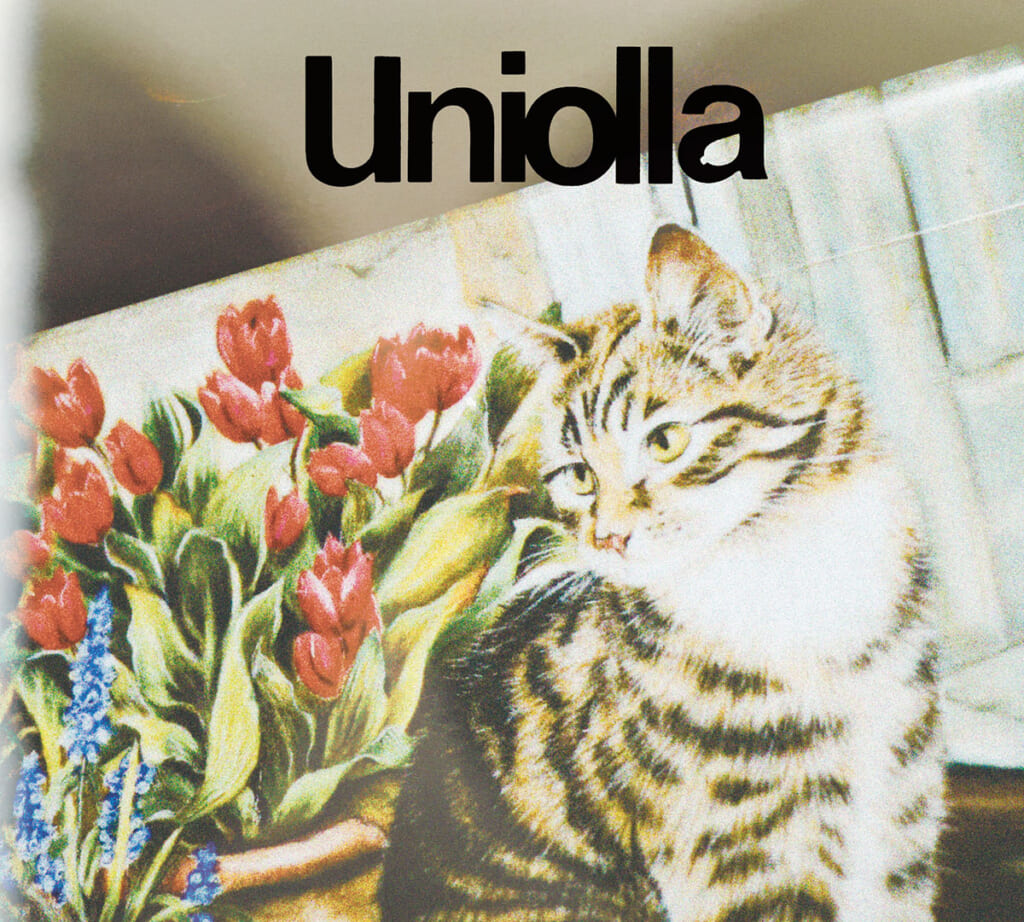
『Uniolla』
Uniolla
ビクター/VICL-65577/2021年11月24日リリース
―Track List―
01.A perfect day
02.無重力
03.絶対
04.Trapeze
05.Sputnik love
06.手探り
07.Knock
08.No pain
09.どうしても
10.果てには
11.あしたの風
―Guitarists―
KUMI、深沼元昭







