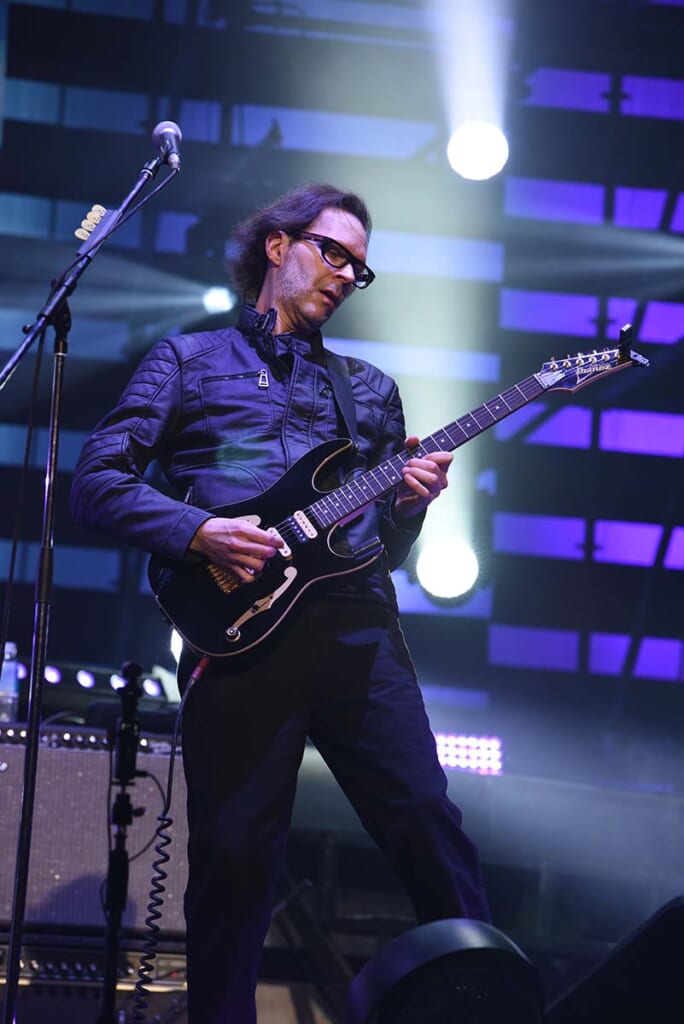MR. BIGのニュー・アルバム『TEN』が2024年7月12日にリリースされた。ギタマガではワールド・ツアー中のポール・ギルバートをキャッチすることに成功、『TEN』でのギター・プレイや使用機材について、たっぷりと語ってもらった。本記事から複数回に分けて“MR. BIG特集”を展開していこう。まずはポール・ギルバート視点で見た、武道館公演〜アルバム完成までの経緯をお届け。
取材・翻訳=トミー・モリー
ブルージィな要素は
僕の指紋みたいなものだね。
北米ツアー中のお忙しいところ取材を受けていただき、ありがとうございます! 昨年の日本武道館でのラスト・ライブ(2023年7月26日)はエモーショナルな雰囲気でしたが、ホームであるアメリカではまた違った雰囲気ですか?
うん! ライブ中、僕は耳を守るため常に耳栓をしているから詳しく聞こえないんだけど、、毎回ビリー(シーン/b)が素晴らしいスピーチをしてくれていて、それがかなり好評みたい。今は大きなロック・ツアーに出ているイメージで、現在進行形の自分を生きてるって感じだね。だから過去や未来に関して、思いをめぐらしているわけではないかな。いつも“今日もロック・ショウが待っている。やってやろうぜ!”って考えているよ。感傷的なイメージはほとんどなくて、純粋にロックンロールをプレイするっていう感じだね。
去年からずっとアジア、南米、ヨーロッパ、北米と長旅をしてきていますが、これはあなたのキャリアの中でも最長のものなのでは?
振り返るとMR. BIGの『Lean Into It』(1991年)が大ヒットした時、どんどん追加公演をしていったんだ。正確には覚えていないけれど、あれに迫るくらい長いツアーになってきたね。
『TEN』はハードロックというより、ブルースのようなムードを強く感じさせるアルバムでした。ギターのサウンドやフレーズは、これまでと違うものを意識したのでしょうか?
そういうのはなかったかな。作曲は僕とエリック(マーティン/vo)で半々で、共作もある。どの曲も独自の世界があるよ。僕はブルースの歌い方が好きでね。ソウルフルなものをたっぷりと感じるし、このスタイルをとても大切にしている。だから僕の作曲したトラックはブルースっぽいサウンドになったんだろうね。
一聴してフリー、バッド・カンパニー、ステイタス・クォーといった、70年代のブルース・ロックのバンドの雰囲気を感じました。そういった狙いはありましたか?
バンド単位でのコンセプトを考えたことはなかったと思う。やっぱり曲ありきで、それらに応じてサウンドができあがっていったね。エリックが作った曲を振り返ると、最初に聴かせてくれたのは「Sunday Morning Kinda Girl」だった。この曲は跳ねるようなポップ・ソングで、ビートルズの「Penny Lane」(1967年)を彷彿とさせるようなところがあったな。それとエリックがギター・ソロのメロディを口ずさんでくれた時、僕はクイーンのようなものも少し感じたんだよね。それをギターで弾こうとした時に“ハーモニーを入れてみたらどうだろうか?”と考えたんだ。結果として、ブライアン・メイのスタイルのものができたよ! “クイーンの要素があるビートルズのようなポップ・ソング”っていう印象かな。
あなたが書いた曲に関しては?
僕が書いた最初の曲「As Good As It Gets」は、エリックが僕のスタジオにやってくる前にラフを作って事前に送っていたデモの中の1つだよ。この曲はアコースティック・ギターで書いたもので、まずザ・フーの「Pinball Wizard」(1969年)みたいにかき鳴らしたあとに、U2のジ・エッジが得意としているディレイを加えたリズム・ギターが思い浮かんだんだ。
色んなアーティストからインスパイアを受けていたんですね。
実はデモでは僕がドラムを叩いているんだけど、叩きながら“これってU2のドラム・ビートじゃん!”って思ったね(笑)。この曲にはブルージィな要素はないかもしれないけど、アルバム全編を通じて、歌い方やプレイの仕方でブルージィさをもたらしているんじゃないかな? もはや僕の指紋みたいなものだね。
やはり、あなたから自然と出てきたものなんですね。
そう。アルバム全体としては60年代のポップ・ソングのようなものが多いよね。例えば「Right Outta Here」ではカポを装着してブルージィなリフを弾いているけど、曲を丸ごとブルージィにしたいとは思っていなかったんだ。もしそうしていたら、単調でくり返しているような印象になっただろうからね。だから大きくコントラストを出すために、中東っぽさを感じるようなエキゾチックなメロディをプレイしてみたんだ。そうすることで一旦ブルースっぽさから離れて、再びブルージィなパートに戻れているんだよね。シンプルなものに簡単な捻りを加えることで、より面白いものを生み出す。そういう工夫は常に頭の中に置いているよ!
今回は共同プロデューサーとしてジェイ・ラストンが参加しています。今作で彼を招いた経緯と、バンドにもたらしてくれたものを教えて下さい。
僕はジェイと作業をするのが好きでね! 僕のソロ・アルバムを何枚かミックスしてくれたし、ワイナリー・ドッグスのアルバムも手がけていたはずだよ。『TEN』ではデモの全部のプリ・プロダクションを僕のスタジオで行なっていて、楽器もすべて僕が一旦プレイしたんだ。そこからジェイと一緒に別のスタジオに入って、ビリーとニックも加わり、僕が仮で演奏したトラックを2人がアップデートするという流れだったね。この時点からジェイが大きく関わっていったんだ。
あなたとジェイの役割分担は?
役割分担としては、僕がプリ・プロダクションのプロデューサーとして曲を形する。ジェイが残りの役割を引き継ぎ、ミックスまで仕上げてくれたよ。
あなた自身で作曲、デモ制作、プリ・プロダクションをした曲がある一方で、エリックやビリーと共作した楽曲もたくさんありますよね。これらはどんな流れで制作したんですか?
制作期間中、エリックは僕のスタジオに何度か来てくれたんだ。僕が作った簡単なデモをデータで送ってもいたよ。
データでもやり取りしていたんですね。
僕が歌ったり、ギター弾いたメロディが入っているだけのデモを事前に準備して、“こんなアイディアがあるんだけど、これをもとにやりたいことを自由にやってみてくれ”みたいな感じで送っていたんだ。その先をエリックが作って完成まで持って行ってくれて、嬉しかったね。「Right Outta Here」と「As Good As It Gets」がまさにそういう曲だ。彼が僕のスタジオに来た時、ついに曲として通してプレイできた感じだね。 ほかにもあったかもしれないけど思い出せないや(笑)。たしかDejaVibeを使ってUni-Vibeみたいなエフェクトを加えた曲のはずなんだけど……。
「Who We Are」ですかね?
そう、それだ! イイ読みをしているね(笑)! この曲には面白い話があって、僕のソロ・アルバムを扱ってきたMascot Recordsというヨーロッパのレコード会社が、ロビン・トロワーも手がけていたんだ。僕は彼のファンでね。それをレコード会社が知っていて、何年か前に“ポール、ロビンの曲を作ってみないか?”と話をくれた。その時に僕が「Who We Are」を作ったんだけど、それを聴いたロビンは“結構です。ノー・サンキュー!”って感じだったんだよ(笑)。
そうだったんですか(笑)。
でも僕は気に入っていて、エリックに聴かせてみたら彼も気に入ってくれたんだ。ただ、その段階ではヴァースくらいしかちゃんとできていなかったから、腰を据えて各パートに手を加えていき、一緒に曲を書き上げたんだよね。エリックと一緒に2時間スタジオにこもって、試行錯誤しながら作り上げた曲だよ。
「Good Luck Trying」、「What Were You Thinking」、「Up On You」はあなた単独の作曲クレジットとなっています。
エリックが“明日は正午くらいに来るよ。じゃあね!”と作業を終えて帰ると、“それまでに何か曲を書いてみよう”って気分になることが多々あったんだ。そこまで意気込まなくても、朝起きたら頭の中にスッと浮かんできて、すぐに書けちゃった曲もあったよ! それで次の日、“エリック、今朝曲が書けてしまったんだ!”と迎えると、エリックは“本当に!?”って感じでさ(笑)。聴かせたら“グレイトだ、これをやろうよ!”となっていたね。だから僕のクレジットの曲は、わりとすぐにできたんだ。
“これはMR. BIG向きだから、その時が来たらリリースしよう”という形で曲作りを行なっていますか? それとも、プロジェクトを念頭に置いて曲を作り始めることが多いのですか?
前者のやり方でできた曲が今回1つあって、それはボーナス・トラックのインストゥルメンタル「See No Okapi」なんだ。これはもともと僕の生徒たちのピッキングのレッスンのために思い浮かんだリフがあって、それをもとに形にしていったんだよ。デモの段階でも、どうもボーカル・ソングには聴こえてこなくてインストにしたんだ。
今回こうやってMR. BIGとして活動しているのは、そもそもフェアウェル・ツアーをやろうという話が原点にあってのことだったと思います。アルバム制作の話はなかったのではと察しますが、いつ頃から制作の話が出たのでしょうか?
僕らのマネージャーが“君らはアルバムを作らなきゃダメだ!”と言ってきて、“OK、じゃあやろうか!”という感じだったよ。でも問題は、それを実行する時間をどうやって作るかってことで……。知ってのとおり、僕らは誰もが忙しかったからね。まずビリーがワイナリー・ドッグスのツアーに出ていたから、彼のスケジュールを抑えることは難しいとわかっていた。エリックもツアーに出ていて、何度も“4日間でいいんだけど来られないかな?”って声をかけまくっていたよ。僕にはいくつか曲のアイデアがあったけど、実際にエリックが僕の家に来て歌を入れるまでは、上手くいくかどうかがわからなかったしね。
色々考えていくと、アルバムを完成させるためには一旦すべてをレコーディングして、あとからトラックを差し替えていくしかなかったよ。だからドラムとベースはすべてインディアナ州にあるスウィート・ウォーター・スタジオで録って、データを送ってもらったんだ。
(ギター編に続く)