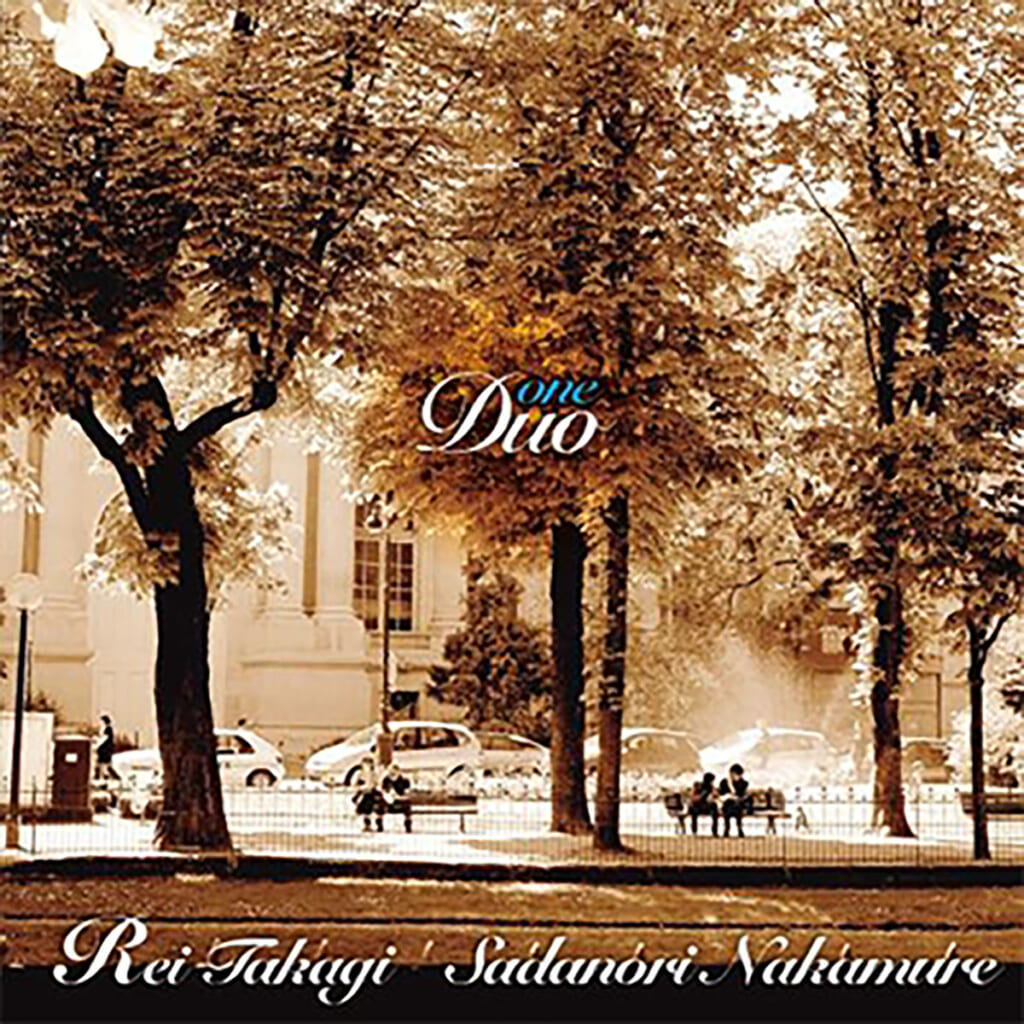『歌姫とジャズ・ギタリスト』で最後に紹介したいのが、後藤芳子と中牟礼貞則。上写真はそんなふたりの名コンビっぷりが味わえる名盤『A Touch Of Love』のブックレットに掲載されたもので、右から中牟礼、後藤、稲葉国光(b)。日本ジャズの歴史に名を刻むこのトリオ作品を題材に、中牟礼がどのような歌伴プレイをしていたのかを改めて見ていこう。
文/譜例作成=久保木靖 写真=『A Touch Of Love』ブックレットより
和ジャズ・シーンの格調を高めたギター弾きと歌手
本企画の最終章は日本が誇る至宝、中牟礼貞則の登場だ。中牟礼が盟友である稲葉国光(b)とともに後藤芳子の伴奏を務めた『A Touch Of Love』(1975年/①)は、和ジャズ・シーンでも傑出したボーカルの名作なのである!
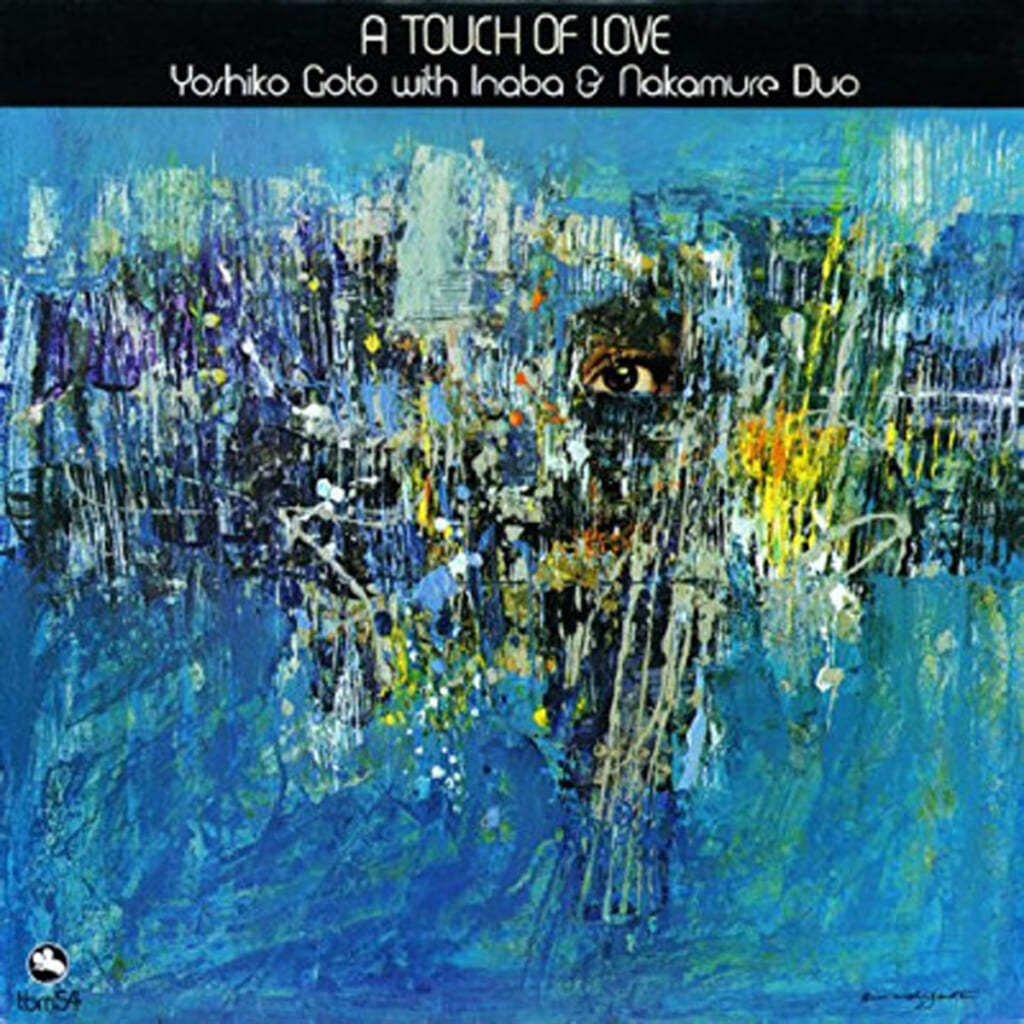
1950年代初頭にプロ・キャリアをスタートさせた中牟礼は、伝説の『銀巴里セッション』(1963年/②)を経て、1960年代後半は渡辺貞夫(as)らとボサノヴァを日本中に広めた。そもそもチャーリー・クリスチャン(g)を研究するところからジャズを始めた中牟礼は、やがてレニー・トリスターノ(p)やリー・コニッツ(as)らの影響を受け、1970年代に入るとジム・ホール(g)にインスパイアされたハーモニー・ワークを取り入れるなど、本邦きっての学究肌ミュージシャン。
一方の後藤もプロ・キャリアのスタートは中牟礼とほぼ同時期。1972年には巨匠レイ・ブラウン(b)を迎えてのLA録音『I’m Glad There Is You』(ギターはジョー・パス!/③)を放つなど、国内外で一目置かれる本格派シンガーだ。


互いに尊重・信頼し合ったレコーディング・セッション
『A Touch Of Love』の誕生には伏線がある。それはギター&ベースのデュオという挑戦的な編成で収録された中牟礼と稲葉による『Conversation』(75年/④)だ。
中牟礼曰く“ジム・ホールとロン・カーター(b)の『Alone Together』(72年/⑤)の存在は知っていたが、それに影響されてやったわけではない”という同作は、クール派的なアプローチからハーモニー重視のプレイへ移行する中牟礼の過渡期をとらえた重要作。この音楽的成功と中牟礼&稲葉の安定感に気を良くしたレーベルの方針で、そこに後藤が参加することになった。
レコーディングは『Conversation』からほぼ半年後の1975年10月。以前よりステージでの共演のあった後藤と中牟礼たちの演奏はスムーズに進んだ。選曲のほか、イントロをどうするか、どこでギター・ソロが入るかなどの構成はすべて後藤が決めたという。収録時の様子を中牟礼に尋ねてみると、 “(後藤さんは)私の芸風を尊重してくれていて、プレイそのものに関する指示や希望は一切なかった。互いに仕草や表情を確認し合って演奏した”と述懐してくれた。


いわゆる“伴奏”とは異なるアプローチでボーカルに絡む
特に小編成の場合、セッション・リーダーに“大人しく刻んでいてくれ”とでも言われない限り、中牟礼は単なる“伴奏”はしない。メロディに対してあたかも管楽器のようにカウンター・ラインで仕掛け、対話するように絡んでいくのが信条だ。これはピアノ的な伴奏を取り入れたジョー・パスや、ギターならではの伴奏に徹するバーニー・ケッセルらと大きく違う点。
そんな特徴がよく現われたのが「My One And Only Love」や「Baubles, Bangles And Beads」で、コード伴奏(これ自体がかなり自由)の中に明らかにオブリガートという意識とは違ったラインを入れてくる。後藤は歌いにくくなかったのだろうかと余計なことを考えてしまう一方で、その緊張感にジャズの醍醐味を存分に感じる。
中牟礼のピッキングの妙を堪能できるのが「And I Love You So」。イントロではフィンガー・ピッキングでコードの各音を同時に鳴らし、Aメロになるとピックで4ビートをサクサクと刻み、サビに至ると先述したようなカウンター・ラインをくり出す。ギター&ベースというシンプルな編成だったことを忘れてしまうくらい曲が展開していることにも驚くはずだ。
唯一ボーカルとギターの完全デュオで演奏された「We’ll Be Together Again」はギター目線で聴いた場合のハイライト。ピック弾きとフィンガー・ピッキングを巧みに使い分けたアルペジオを主とした伴奏から、途中、低音のカウンター・ラインという珍しい技を挟み、エンディングではクリシェ・コードが華やかに舞う。ちなみに後藤と中牟礼はこの曲のタイトルどおり、10年後に『Hello』(1985年)で再共演を果たしている。
そのほか、稲葉のベースが唸りを上げる「How Insensitive」や、ギター・ソロが歌いまくっている「I Should Care」もマスターピースだ。
“デュオ名人”という側面も持つ中牟礼貞則
『A Touch Of Love』は3人編成だが、そもそも1950年代から高柳昌行と2ギターによる活動をしていたという中牟礼にはデュオ名人という側面もある。高樹レイ(vo)との『DUO-one』(2015年/⑥)や、岡安芳明(g)との『Guitarist』(2016年/⑦)は記憶に新しい。
近年のライブではベースやピアノはもちろんのこと、ドラムとのデュオにもチャレンジしている。また聞くところによると、現在ピアノとのデュオ・アルバム制作に取り組んでいるとか。御年87の現役ミュージシャンの挑戦に目が離せない。