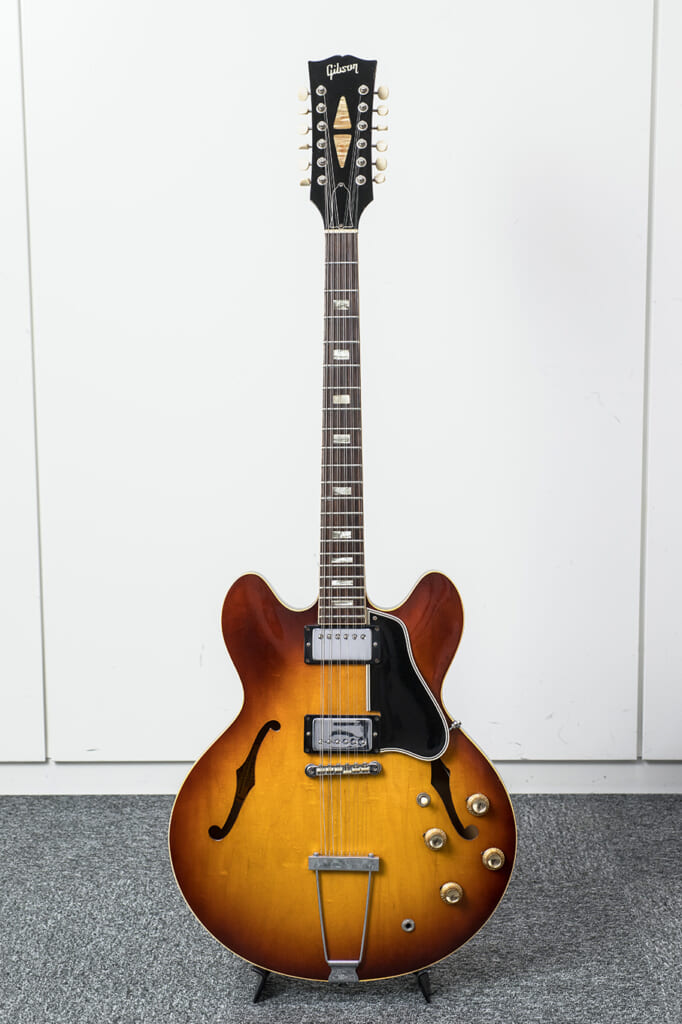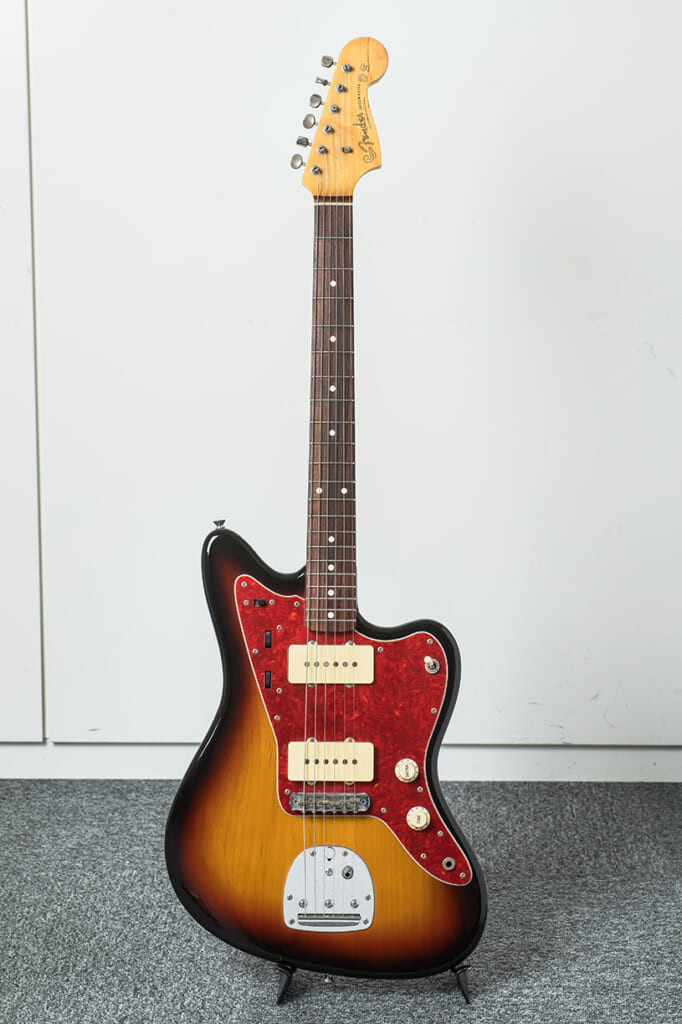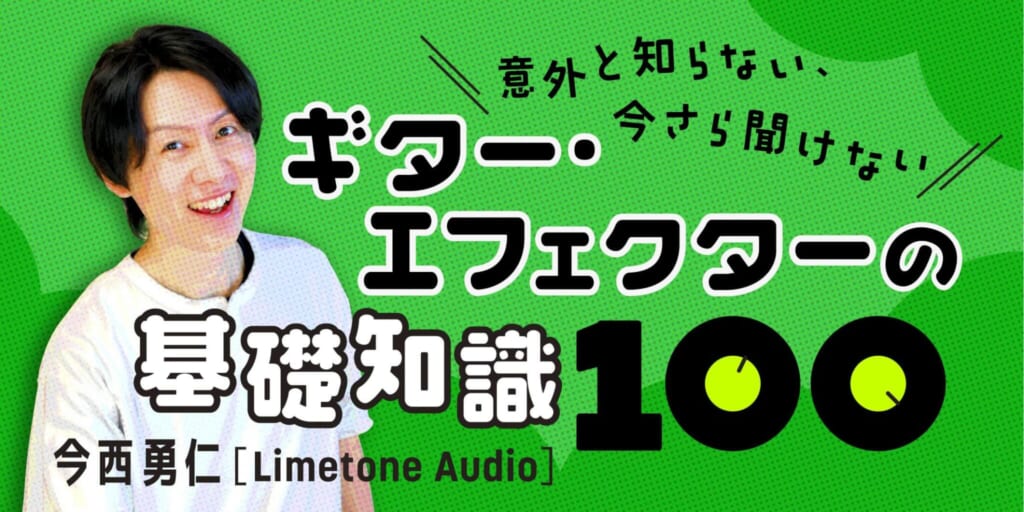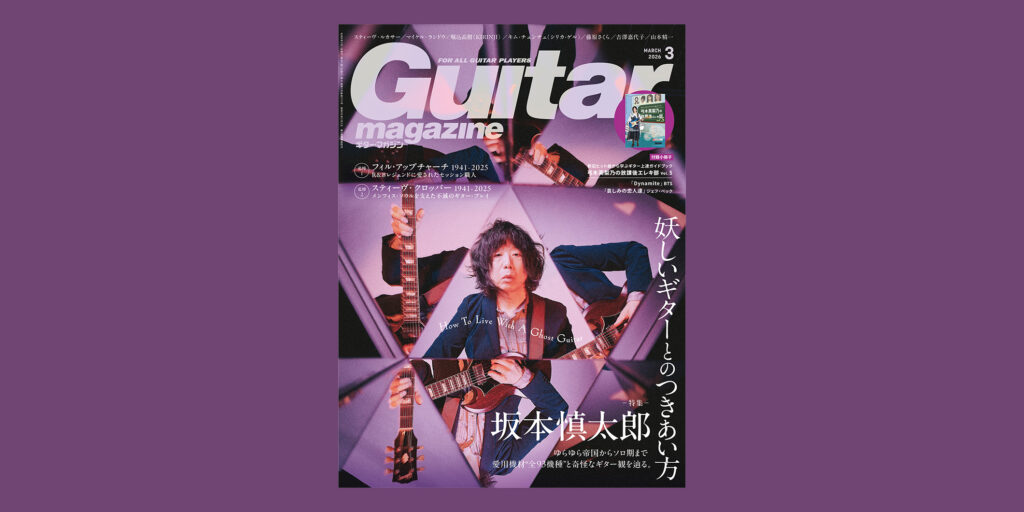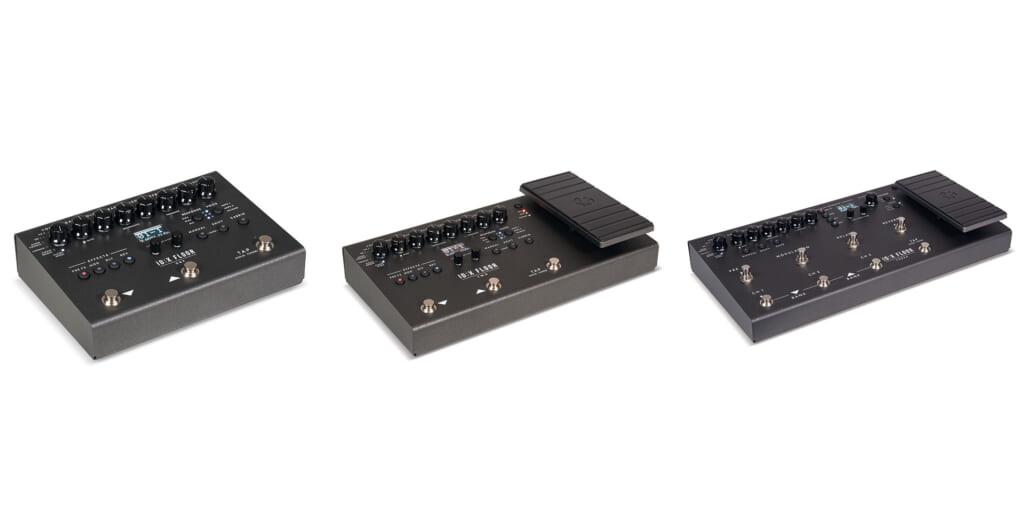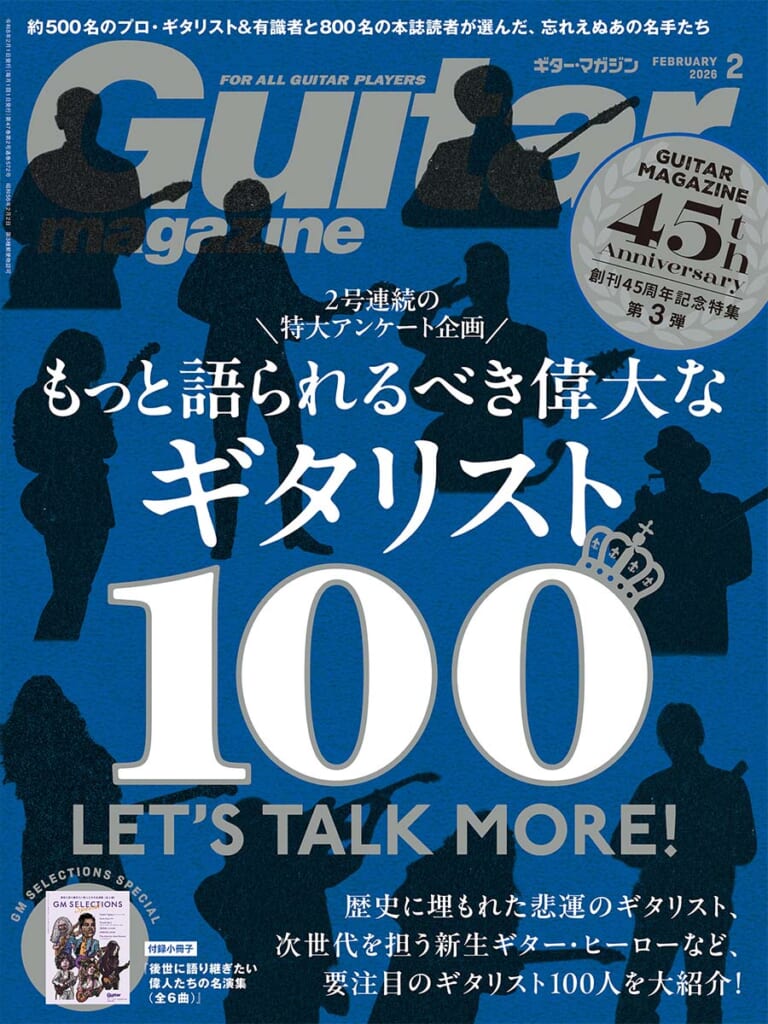THE TREESの最新作『Reading Flowers』のインタビュー時、アルバムで使用した機材を有馬嵩将(vo,g)&荏原優太郎(g,cho)の2人に持ってきてもらった。ここでは前回のインタビューに引き続き、アルバムのプロデューサー、菅原慎一にも案内人となってもらい、使用機材について語ったインタビューをお届け。各ギター&ペダルボードの解説もお見逃しなく!
インタビュー/文=辻昌志 写真=小原啓樹
菅原さんのペダルボードとほぼ完全に似せましたね。
──荏原優太郎
『Reading Flowers』の使用機材について教えて下さい。機材についても、菅原さんからも助言があったのでしょうか?
荏原 そうですね。機材は菅原さんから借りたものも多いです。
菅原 荏原君の今のボードの中身を見ると、今の俺とほぼ一緒……。
(笑)。レコーディングのあと、実際に買ったんですか?
荏原 そうですね。もともと似ていたんですが、それをほぼ完全に同じにしたという(笑)。そのペダルは今作のサウンドの肝になってる感じですね。
肝というのは?
荏原 strymonのmobius(マルチ・モジュレーション)を使ったことが大きいです。今まで僕が持ってたコーラスとは違う揺らぎ感があって、特に「Clover」ではmobiusが活躍してますね。あと、アルバム全体を通じたクリーンのトーンは、BadCatのSiamese Drive(オーバードライブ)が核になっていると思います。
Siamese Driveも、菅原さんが持っているペダルですよね。クリーンのトーンをそのペダルで調整したと。
菅原 Siamese Driveは音の硬さやトーンを直感的にいじれるところが良いんですよ。それが重要なんですけど、これには僕の持論があって。ギターはやっぱり、まずクリーン・トーンの出音をしっかり決めることが大事だと思うんです。彼らがこれからガッツリやっていくにあたり、現場で音の硬さやEQなどを自分で調整できるようになることがすごく大切で。
なるほど。
菅原 あと、僕も荏原君も基本的にフェンダーのツイン・リバーブを使ってるんですけど、ミッドをフルテンにするっていうのがポイントです。特に彼のメイン・ギターのストラトだと、ギターの旨みが一番出ると思うんですよね。アンプのツマミは基本的にミッドをフルテン、そのあとにローなどを足す、なども教えていましたね。
ボーカルに集中するために、自分の出音を決めたほうが良い。
──菅原慎一
有馬さんも菅原さんからのアドバイスを受けたわけですよね。それを聞いて、自分のサウンドを確立できたという実感はありますか?
有馬 そうですね。僕は今回のアルバム制作で初めてアンプを買ったんですよ。VOXのAC30です。まずは“自分の音”っていうベースを持っておいて、違う現場に行く度に微調節して変えるくらいがいい、っていうのを教えてもらったので。
菅原 それは口を酸っぱくして言いましたね。特に有馬君はボーカル・ギターだから、“ボーカルに集中するためにも、自分の出音っていうのをある程度決めたほうがいいよ”と。そしたら、すぐ買いに行ってました(笑)。
素直ですね(笑)。歪みペダルは何を使ったのでしょうか?
菅原 ペダルの歪みをたくさん使うというよりは、ギターのほうを替えて音を作っていきましたね。ただ、自分が持っていたローランドのRE-201(テープ・エコー)は活躍しました。「Marron」や「Primula」は、実はその自然なテープの歪み感がけっこう入ってるんですよ。
荏原 「Marron」は少しまろやかなコンプかかったテープの歪みが気持ち良いですね。
菅原 アナログっぽさもTHE TREESの魅力なので。プロダクションは現代的なのは担保しつつ、機材は古めのものを使ったほうが、2人の好きなバンドのサウンド感には近付くと思いましたね。
Arima’s Guitar
Ebara’s Guitar
Arima’s Pedalboard

【Pedal List】
①BOSS/TU-3(チューナー)
②Maxon/OD-820(オーバードライブ)
③Ibanez/TS9(オーバードライブ)
④Love Pedal/Amp Eleven(オーバードライブ)
⑤BOSS/DC-3(ディメンション)
⑥tc electronic/Hall Of Fame(リバーブ)
⑦BOSS/DD-7(デジタル・ディレイ)
⑧VOODOO LAB Pedal/Power 2 Plus(パワー・サプライ)
歪みの使い分けがポイント
有馬が使用するペダルボード。接続順はまず、ギターから①へ入る。⑦まですべて直列でつないだのち、アンプへと接続。
②は基本的に踏みっぱなしにし、クリーン・ブースター的に使用。そのためドライブは9時前後と薄めに設定する。メインの歪みペダルは③。こちらはドライブを11時に設定し、クランチ気味にサウンドメイク。同じく歪みの④だが、こちらは単体で踏むことが多い。”金属的なジャキっとした音だが、ローも出る”といい、③とはシチュエーションで使い分けるそうだ。“揺れないコーラス”として有名な⑤は“きれいなクリーン・トーン”にしたい時に踏む。リバーブは基本的にアンプ搭載のものを使うが、さらに深いリバーブが必要な時は⑥をオン。⑦はおもにショート・ディレイや飛び道具として使用するという。
Ebara’s Pedalboard

①Korg/Pitchblack PB-01(チューナー)
②Bad Cat/Siamese Drive(オーバードライブ)
③Xotic/EP Booster(クリーン・ブースター)
④Ibanez/TS-9(オーバードライブ)
⑤JHS Pedals/Morning Glory V4(オーバードライブ) ⑥stymon/mobius(マルチ・モジュレーション)
⑦BOSS/RV-6(デジタル・リバーブ)
⑧Line 6/DL4(マルチ・ディレイ)
クリーン・トーンへのこだわり
荏原のペダルボードがこちら。接続順はギターから①に入り、すべて直列で⑧までつないだのち、アンプへと接続。
②は2チャンネル仕様のオーバードライブだが、荏原はCh1(右スイッチ)を常時オンとし、クリーン・トーンのサウンドを作る。歪ませる時は④をオンにし、ドライブは9時前後に設定。ガツンと歪ませたい時は①のCh2と組み合わせる。③はライブ専用機。クリーンの音を際立たせたい時に踏む。⑤の歪みペダルは、今作だと「Mimosa」の録音で使用。トーンを上げると“パリパリ”の音になるため、絞って使用する。⑥はプリセットを設定し、タイプは“Chorus”をおもに選択。⑦は“ROOM”モードで使う。⑧はプリセット設定で使用し、ショート/ロング・ディレイのほか、リバース・ディレイ用としてオン。
作品データ
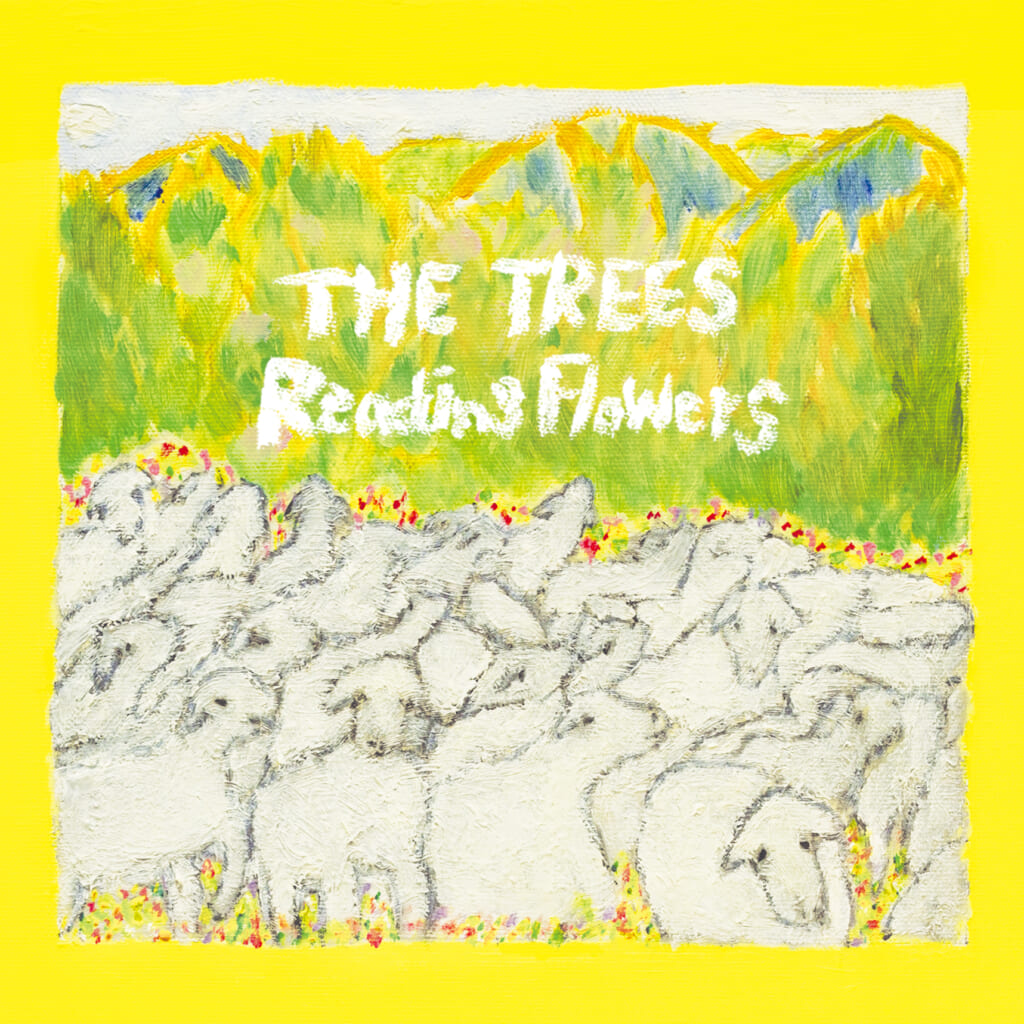
『Reading Flowers』
THE TREES
P-VINE RECORDS/PCD-83037/2021年6月23日リリース
―Track List―
1.Clover
2.Edelweiß
3.Primula
4.Iberis
5.Marron
6.Lilac
7.Zinnia
8.Mimosa
9.Chloranthus
10.Coleus
―Guitarists―
有馬嵩将、荏原優太郎