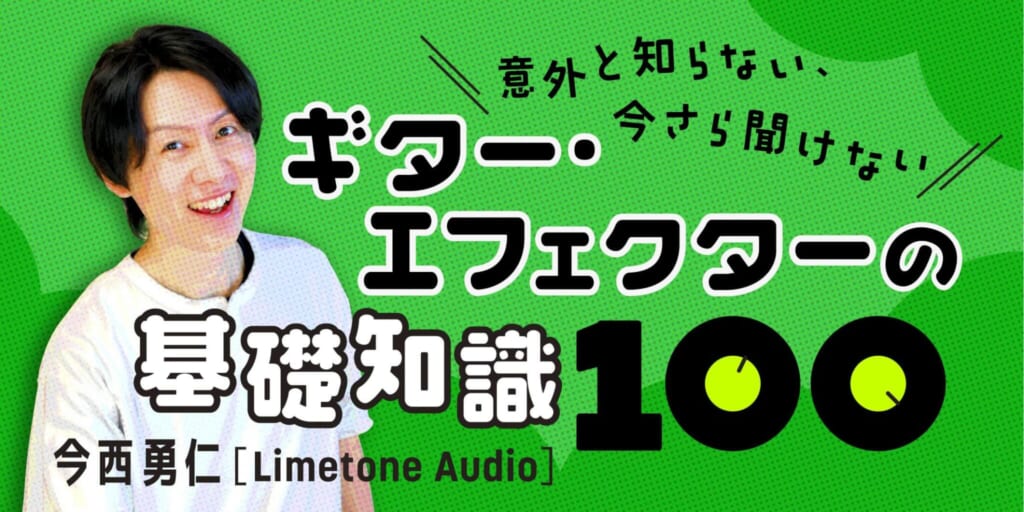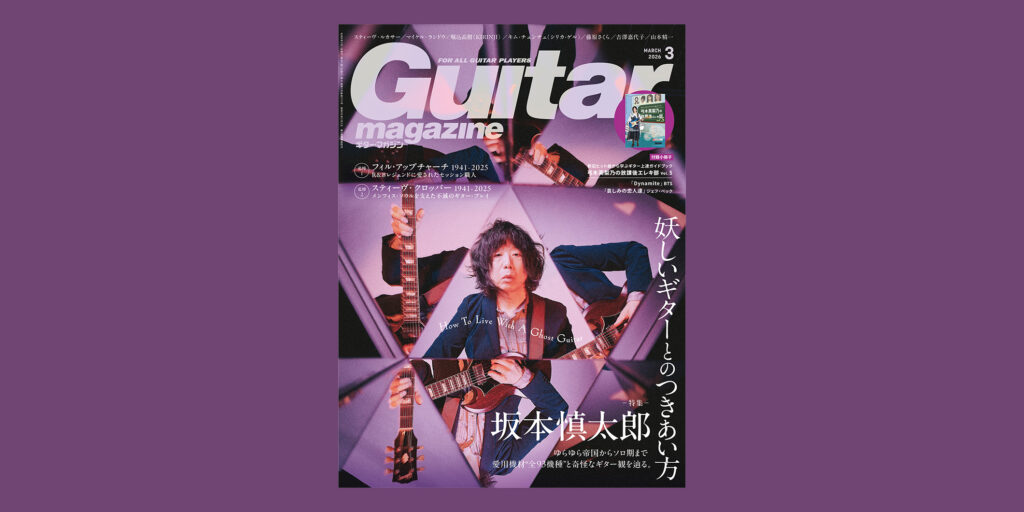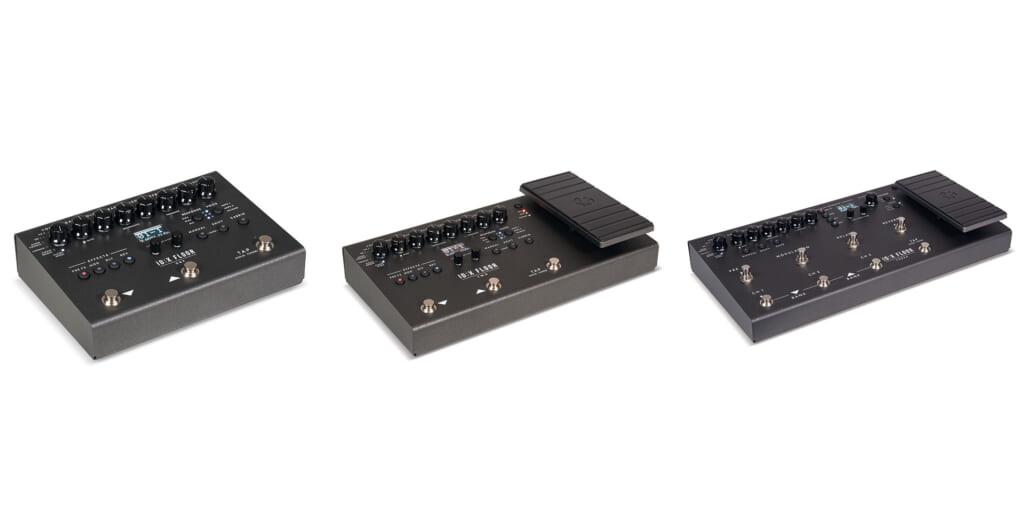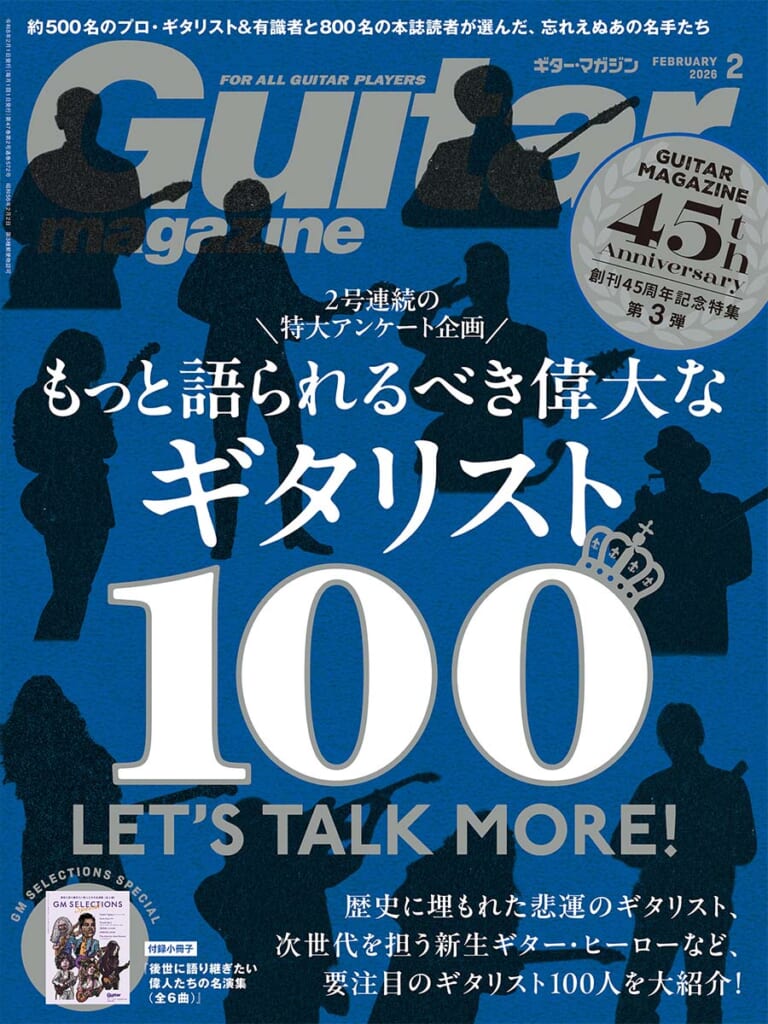10月に2年半ぶりのニュー・アルバム『WINDORGAN』を発表し、久しぶりの全国ツアーも大盛況のYogee New Waves。ヨギーといえば新世代のシティ・ポップを鳴らすバンドと位置付けられてもう何年も経つが、それ以前に彼らは強固なギター・バンドである。それを改めて見せつけたのがこのたびの新作で、角舘健悟(vo,g)と竹村郁哉(g)の両輪からなる七色の演奏が痛快だ。特に竹村のリード・プレイは以前にも増して存在感を拡大した感あり。新作とギターについての話を軸に、雑談っぽく自由に語ってもらおう。最新の使用機材は近日公開!
取材=山本諒 写真=山川哲矢

“ラブリーな曲を作ろう”と
思ってたところはあった。
(角舘)
久しぶりのアルバムですが、コロナ禍に入る前から作っていたんですよね?
角舘 そうなんですよ。
竹村 やってたね。
角舘 ちょっとカレンダー見ようかな……うん、2020年1月ぐらいが作曲期間だ。
竹村 なんか、健悟の家にめちゃくちゃ行ってた記憶があるんだよな。
角舘 そうだ。とにかく黙々とやってた気がする。記憶が曖昧ですけど……ホントに、時間が空いちゃったから。とにかく2019年の暮れくらいから作っていて、2020年の2月くらいからレコーディングが始まったけど、コロナで中断したんです。そこで1回みんなで離れ離れになっちゃって、完全に止まったんですよね。
竹村 止まったなぁ……。
角舘 で、“どうしよう?”みたいな。結局、1年ぐらい別々の状態で、それぞれが修行というか。色々考える時期があって。
竹村 で、今年の1~2月ぐらいにまた動き始めましたね。
その空白の期間は何をしていましたか?
角舘 KCEE(DJ,etc/Suchmos)の家で曲作ったりしてました。あと、昔ヨギーでギターをやっていたShinpe Uedaくんと家でトラック作ったり……ほかにもエレピ弾いたりドラム叩いたり、弾き語りもやりましたね。とにかく楽器と音楽にまつわることは全部やった気がします。けど、バンドはやっぱ楽しいよね。
竹村 まぁね。
角舘 そこに戻ってきたっていう。
竹村 僕もあの期間は、朝起きてすぐDAW立ち上げて、曲作ってましたね。曲のタネっていうか、デモみたいなのをずっと作ってた。
久しぶりにバンドで集まって音を出した時は解放感がありましたか?
角舘 でも、わりと憔悴してて。久々すぎたのもあって、すごいゆるめのサイケなセッションをずっとしてた気がするな。身にならないやつを(笑)。
竹村 シンプルに、バンドとしての一体感がほころんでたよね。グルーヴ感はもちろん、“コイツはこういう感じで来るよね”みたいな感覚もみんな忘れてるし。“あ、初めまして”みたいな空気感というか。
角舘 うん。それぞれエネルギッシュな人間だから、1人で考えたこともたくさんあったんだと思う。それまでは同じ飯食って、ガキのテンションで土足で踏み込んでたけど、“それぞれがテリトリーを作って、そこで培ったものを活かす”的な関係に変わっていく感覚はありましたね。
さて、新作『WINDORGAN』を作るにあたって設けたテーマはありましたか? 過去の3枚のアルバム(『PARAISO』、『WAVES』、『BLUEHARLEM』)は“島三部作”と言われていますが。
角舘 “街に帰ってこよう”みたいな話はしてましたね。“架空の島じゃなく、自分たちが住んでる街を見つめ直してみよう”って。で、そうなってくると僕らの場合、シティ・ポップな作風になるのか?と思ったら、なんかフォーキーな世界に向かっていったんです。
竹村 そうね。シティ・ポップの中でも、都市部じゃなくて、それこそ昔の西岡恭蔵さんとか……。
角舘 そうそう。一緒に聴いたね。
竹村 うん。アーバン(都会)とサバーバン(郊外)の間というか。そういう街の情景が見えるといいよね、みたいな話はしてたな。
角舘 大滝詠一さんの1st(『大瀧詠一』/1972年)とかね。あれもう、大好き。
竹村 そうそう。で、健悟が弾き語りで曲をやってる時に、少なからずああいう世界と近いものを感じたというか。“そこを押し出すアレンジって面白いかもね”みたいな話はしましたね。
確かに、フォーキーな要素は前作より増えました。
角舘 そうですね。で、都市と音楽っていうものに関して、今回作るにあたって俺は1つ意識があったんですよ。……これ、全然ギタマガっぽい話じゃないですけど、大丈夫ですか?
どうぞどうぞ(笑)。
角舘 2019年当時、ヴァンパイア・ウィークエンドの新作(『Father of the Bride』)をずっと聴いてて。その年の5月に僕はニューヨークに行ったんですけど、街を歩いているとあのアルバムがずっと脳内で流れるんですよ。なんか毒でもなく良薬でもない、あのフラットな“生き物としての音”みたいな世界観で、めちゃくちゃ感動したんです。都市部に生きるアーティストとしての“ただの音”みたいな。なのにもの凄くラブリーで、けどブルーで、すべての感情をちゃんと表現している。で、そのニューヨークで感じたことを東京という自分のベースに置いてみたところ、けっこう合ったんです。だから、“ラブリーな曲を作ろう”と思ってたところはあったかな。スカしたりせず、というか。
竹村 今振り返ってみると、東京っていう街を今一度見つめた時期だったかもしれない。結局延期になったけど、東京オリンピックも控えてたし。僕らもアジアツアーを経て、なんか自分の街を客観視できるようになってたから。
角舘 うん。“期間中は外国人もいっぱい来てライブに来てくれるだろう”と期待をしつつ、“日本というよりは人類的に響く作品にしたい”って思いもありましたね。いろいろ頓挫しましたけど(笑)。……でも、個人的にはヴァンパイア・ウィークエンドのプレーンな世界がイメージにあって、だから今回アコギはギルドじゃなくてマーティンを多用したんですよ。
竹村 急にギターの話に戻った(笑)。
うまいことギタマガの話につなげてもらって(笑)。
角舘 無理くりですけど(笑)。ギルドはちょっと昭和的な雰囲気があるんですけど、マーティンはもうちょっとピアノっぽいというか、プレーンなイメージなんですよね(※使用機材は近日公開!)。
ギタリストとしての
強いアイデンティティが出た。
(竹村)
新作のギターの話ですが、よりギター・バンドとしての純度が上がったような印象です。竹村くんはほとんどの曲でギター・ソロを弾いてますよね?
竹村 確かに、振り返ると多いっすね(笑)。
角舘 でも、必要なんだよな。曲を作る時にいつもソロを用意しちゃう。好きなんですよね。
新作を聴いていて思いましたが、ヨギーの楽曲って、ギター・ソロへ行く前に助走をつけるようなパートが多いですよね? “ソロ来るからな、待ってろよ~”的な(笑)。
竹村 ああ、確かに。
例えば「SISSOU」だと、ソロ前の静かになるパートでフィードバック音を出してからソロになだれ込んだりとか。
角舘 そうなんですよ。なんか、シンプルにブッ飛びたいんですよね。バンドだし。ギター・ソロがあると、そういうブッ飛びたいポイントがしっかり作れるっていうか。
竹村 エンジニアの柏井日向さんもそこを意識してか、ギター・ソロの音量が年々上がってるんだよね(笑)。
角舘 良い傾向だ(笑)。やっぱもう、爆音すぎて音割れしてるぐらいで良くて、マスキングしてない感じが理想ですよね。
あとギター・ソロへのお膳立て的なパートでカッコいいなと思ったのが、「Night Sliders」。ソロ前の“ジャッジャッジャッ!”っていうブレイク、あそこだけ何回も聴きましたよ(笑)。
竹村 ありがとうございます。
角舘 あそこはみんなで爆笑しながら、“おもろ!!”って感じで作りました。「Night Sliders」はちなみに、ボンちゃん(竹村のニックネーム)の曲ですよ。デモとオケは完全に彼が作ったもので。
え、そうなんですか? 曲はこれまでずっと健悟くんが書いてましたよね?
角舘 そうそう。でも、なんか“俺は曲を作る、ボンちゃんはギター弾く”みたいな関係でしばらくやっているうちに、俺がちょっとワガママを言うようになって。で、“自分が弾きたいって思う曲、ちょっと作ってみてくれ”みたいな話になって……で、できたのが「Night Sliders」です。
竹村 うん、そうだね。
角舘 すごいギタリストっぽいというか……“あ、ボンちゃん、こういうのやりたいんだ”って思いました。
竹村 ちょっとそう言われると恥ずかしいけどね。
角舘 いいじゃないですか。
竹村 確かにアゲアゲな時に作ったんですけどね。フジロック帰りくらいの時に作ったんですよ。だから、超テンションが高いというか(笑)。
角舘 ギターがかっけえ! みたいなね。
竹村 ひとまずリフから始めて、Aメロ/Bメロ/サビくらいまで作って。そのまま健悟と2人で速攻スタジオ入って、それでデモをツルッと作って録った感じですね。……ギタリストっぽい曲っすよね(笑)。
ソロもファズをかけてどこかハードボイルドですね。
竹村 ハードボイルドです。これまで全然自覚なかったんですけど、自分にもあるんですよね。ギタリスト的な強いアイデンティティが。
角舘 あるんでしょうね。
竹村 ライブであの曲のソロを弾いてる時、顔カッコいいっすもん。
角舘 自分で言うのかよ、それ(笑)。
ギタリスト=竹村郁哉の感情がむき出しになった曲かと思いますが、健悟くん的にこういうところを期待していたようなところはありますか?
角舘 ありました。シンプルに彼のストラトと、俺のES-345で比較しちゃうと太さで勝っちゃうんですよ。セッションしてても、自分は落ち着きがないから気付いたらギター・ソロを自分で弾いちゃったりして。“ボンちゃんにもっとこう、音でブチ殺してほしい”って思いはずっとありました。そしたら、まさにそういうのを持ってきたから“やったな!”みたいな。
「Night Sliders」のソロはこれまでにない、ちょっとサディスティックな雰囲気もありますよね。
角舘 わかるわかる。
竹村 それ褒めてる(笑)?
もちろん。ギターと暴力性は表裏一体というか(笑)。
角舘 サドっていうのは、近くにいるからめっちゃわかります。俺の場合、どうしても美しさとか、悲しさとか、ノスタルジー的なほうに持っていきがちなんだけど、ボンちゃんは“サドだな……”っていう、怖い時がある。“この人、真顔でブン殴るタイプだ”みたいな(笑)。
竹村 今作は確かに、ファズとかよく踏んでますしね。「White Lily Light」とか。
角舘 あの曲も、ボンちゃんがギター・ソロ乗せたらちょっと暴力的になりましたよ。
竹村 ちょっとアウトさせたフレーズでやってみたからね。あそこは自分の役割として、“暴風雨みたいに曲の世界観を崩したい”と思ってた。
角舘 うん。曲のテーマ自体はきれいで美しいものなんですけど、それだけだとロック・バンド的じゃないし、“人生って紆余曲折あるものだよな”って思って。だから、きれいなだけじゃなくてグチャっとしたところも入れたかったんです。“グチャグチャになるからスッキリした日が来る”っていうか……そこを表現したかったんですよね。俺、きれいなものを作ったあとにブチ壊してほしい、みたいな、マゾ的なモードになる時があるんですよ(笑)。そういう時に、ちゃんとサドしてくれるのがボンちゃんみたいな。
バランス取れてますね。
角舘 でもマゾ的感覚で言うと、思いっ切り来ないと逆にムカつくんですよ。恥を忍んでマゾだと打ち明けているのに、サドが本気を出さないっていうのは失礼なんですよ(笑)。
竹村 でもさ、サドマゾの真理って結局、マゾが主導権を握ってるみたいな話もあるじゃない。
角舘 そうね。マゾが場を作るという。
竹村 まさにそうだよね。マゾが“さあ、好きにどうぞ”って場を用意してくれるからサドが存在できるのよ。
なにこのインタビュー(笑)。
角舘 月刊ボンテージ(笑)。
竹村 “ムチ100選”みたいなね。やめましょうか(笑)。

“曲に合う音符感”から
ハズして弾きたい。
(竹村)
健悟くんのギター・スタイルはカッティングが1つの武器だと思いますが、弾く際のこだわりはありますか?
角舘 ジャカジャカ弾くんじゃなくて、“ストップ感”は凄い意識してるかも。つまり音を切ってストップさせて、すかさずスネアが“タッ!”て来るとか、そのへんはめちゃくちゃ大切にして弾いてます。いわゆる“休符を弾く”ってやつですよね。そこをあえてズラしたりとかして、グルーヴを変な感じにさせたりもするかな。
カッティングのタッチはソフトじゃなくてかなりハードめというか、打楽器的ですよね。
角舘 ドラムとかパーカッションのイメージでやっちゃってますね。
竹村 ギタリスト的なカッティングじゃないかもね。
角舘 もともと自分はドラムをやってたので、リズムのアクセントに関するこだわりってけっこう強いんですよ。ライブだと、自分のカッティングで“ここが絶対気持ちいいから!”みたいにリードすることもあります。で、リズム隊もそこに気付いてくれて、呼応してきたら逆に俺はそのパターンをやめてジャーンと伸ばしてみたり。そういうグルーヴのやりとりを現場でやってるような時はありますね。
竹村 そこら辺のコントロールは、かなりやってくれてるのがわかるな。ボーカリストとして歌いながら弾きつつ、いつもバランスは見てる。過剰になってる時には白玉で音符を減らしたり……柔軟さがあるカッティングを弾く印象ですね。
次は竹村くんのリード・ギターについて。「Ana no Mujina」では中盤とアウトロで2つのソロがありますが、前者はカントリー、後者はラテン調と明確に弾き分けていて、1つの聴きどころだと感じました。
竹村 デモの段階で明確に世界観を分けようってことになってたんです。「Ana no Mujina」は、弾いていて一番楽しい曲ではありますね。
角舘 なんか、フレーズが能動的ですよね。アウトロのソロは“リズムで聴かせたいんだな”みたいな意思がよくわかる。
竹村 ああいうリズムで弾く感じは、個人的にアイディアが出てきやすいです。けっこう、笑えるフレーズがたくさん弾けたっていう満足感はあるかな。
フレーズは事前に組み立てることもあると思いますが、何か気をつけていることは?
竹村 驚きは1個、どっかに用意するようにしてます。“こなし”でソロを弾くことほどつまんないことないから。なんか、“自分のソロでプッと笑って欲しい”って思いが強いんだよな。
角舘 “吹き出してくれ”と思ってギター・ソロを弾いてます、と。
竹村 そう。ギャグ漫画みたいな、“何コレ?”っていうのは、ちょっとやっぱどっかに欲しいよね。
角舘 可愛い感じとかね。
竹村 めちゃくちゃいいプレイって、聴いてて爆笑しない?
角舘 わかるわかる。
竹村 なので、1個フックというかポイントは作ってますね。感覚的な話なんですけど、“楽曲に合った音符の数”ってあるじゃないですか? “この曲はこれぐらいの音数でフレーズを弾くのが最適”という。で、そこはハズすように弾きたいなっていうのもあります。曲の音符感にマッチさせて弾くと、“まあ、そうだよね”みたいな感じになるから。
角舘 それって感覚的にやってるんでしょ?
竹村 そう。なんか、フリースタイルのラップがカッコいいのってそういうとこじゃん。“あ、8で普通に乗せていると思ったら、急に3連入って、最後16で駆け抜けるんだ”みたいな。そういうのが好きなんで、ギター・ソロにもそういう意識が出てるかもしれないですね。
良い曲には、良いギター・ソロがあると思うんです。
(角舘)
ヨギーは初期の「Climax Night」の頃から印象的なソロがありますが、楽曲の中でギター・ソロを設ける効果とはなんでしょう?
角舘 歌が終わって、自分の感情がいなくなった瞬間にバトンタッチしてほしいんですよ。で、良い曲にはやっぱ良いギター・ソロがあると思うんです。俺、中学生の時に東京事変をよく聴いてたんですけど、カッコいいソロがたくさん入っていて。そこで、J-POPとバンド音楽の違いに気づいたというか……。つまり、バンドにはブッ放せるキャノンが付いてるんです。バンドをやっている以上、そこを使わないともったいない。あとは、“歌が全部語ってしまうと面白くないな”って思いがあって。言葉にできない瞬間ってやっぱあって、“音”でしか表現できない時にギター・ソロがバトンを受け取ってくれると、凄く気持ちいいんですよ。
なるほど。
角舘 あとは、ギターの音がね、ホントに好きなんです。シンセもピアノも好きだけど、ギターの音って、やっぱ最高っすよね。めちゃくちゃ有機的だし。
竹村 そうだね。
角舘 “こんなプレイヤーと身体的に1個になってる楽器もないよな”とも思う。ギタリストっていう生き物が、職業を得てちゃんと飯を食えてるのが理解できるっていうか(笑)。そのくらい、華のある楽器ですよね。
竹村 なんか、前の『BLUEHARLEM』の時はシンセとかたくさん入れていて、新作でももちろん入ってるけど、“ヨギーはギター・バンドだな”っていうのは今回めっちゃ感じたんですよね。実際、自分のギターもいつも以上に鳴ってるし。ヨギーにとってギターとは何かって考えると、個人的にはやっぱり“生命線”というか。あって然るべきものですよね。

作品データ

『WINDORGAN』
Yogee New Waves
ビクター/VICL-65563/2021年10月13日リリース
―Track List―
01. SISSOU
02. to the moon
03. You Make Me Smlie Again
04. Night Sliders
05. JUST
06. Ana no Mujina
07. あしたてんきになれ
08. windorgan
09. Toromi Days feat. Kuo (落日飛車Sunset Rollercoaster)
10. Jungrete
11. Long Dream
12. White Lily Light
―Guitarists―
角舘健悟、竹村郁哉