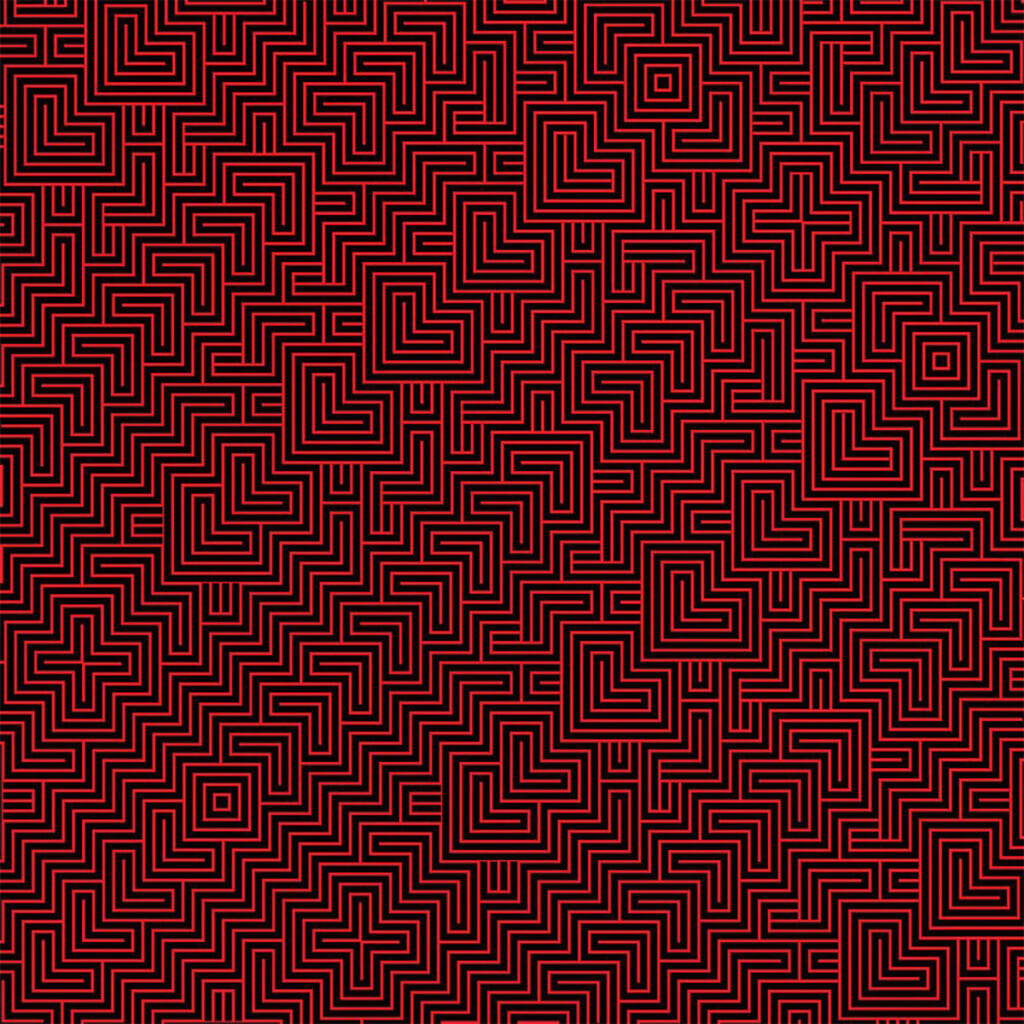現代サイケデリック・ロックの雄=ザ・ブラック・エンジェルズ。日本ではまだまだ馴染みがない彼らだが、現代シーンにおいてはずせない存在だ。彼らの地元である米オースティンの大型サイケ・フェス“LEVITATION”の主催者であり、フレーミング・リップスやプライマル・スクリーム、スピリチュアライズドなどとも共演。テーム・インパラやMGMTらが頭角を現わす前から“ネオ・サイケデリアの旗手”と称されてきたバンドである。
今回は新作『Wilderness of Mirrors』のリリースに際して、バンドのリーダーの1人でありギタリストのクリスチャン・ブランドと、2013年に加入してから今やバンドに欠かせないエッセンスを放つジェイク・ガルシア(g)にインタビューを行なった。彼らのプロフィールやバンドの音楽性、作品制作の話などから、その正体を紐解いていこう。
取材:錦織文子 翻訳:トミー・モリー Photo by Getty Images
ヴェルベット・アンダーグラウンドの、ミニマムなのにインパクト溢れるギターには衝撃を受けたよ。
──クリスチャン・ブランド
ザ・ブラック・エンジェルズは2011年のフジロックで初来日しましたが、当時は日本でも話題になっていましたよ。
クリスチャン・ブランド(以下CB) ありがとう。俺らは確かテントのステージでプレイしたんだよね。あのフェスは木々に囲まれていて、最高にクールだったよ!
日本のもっと多くのリスナーにあなたたちの存在を知ってほしいので、まずはバンドのプロフィール的なことから教えて下さい。どのような経緯でバンドを結成したんですか?
CB 俺と、アレックス(マース/vo, b, syn, etc.)はテキサス州のシーブルックという街で育ち、俺が13歳でアイツが11歳の時からの知り合いなんだ。中学〜高校と一緒の場所へ通い、フロリダ州の大学に通うために俺は一度地元を離れたけど、2002年にオースティンの大学に転入するために再び地元に戻ってきた。オースティンへ行ったらバンドを始めたいと思っていたんだけど、偶然にもアレックスがオースティンにいて再会したんだ。アレックスはその街で“Elevation 33”っていうアコースティックなバンドをやっていることを知って、“一緒にバンドを始めないか?”と誘ったんだよ。
地元からの仲間だったんですね。
CB うん。でもお互い一緒に音楽をプレイしたことがなかったし、そもそも俺はギターを弾き始めたのは二十歳になってからだった。アレックスだって音楽をプレイし始めたのはけっこう遅かったんだよ。でも、話を持ちかけた翌日には2人で5曲をレコーディングし、それが俺らのバンドのスタートのきっかけとなったんだ。その後すぐに本格的にメンバーを探し始めて、ステファニー(ベイリー/d)が加わってからは、オースティンに一軒の家を借りてそこに住み、いつでもジャムれる練習部屋を作って、バンドに重きを置いた生活をしていったよ。これは俺らが生きていくうえでやりたいと思っていたことだったし、100%を捧げるつもりだったんだよね。
ジェイク・ガルシア(g)が加入したのはどういうきっかけですか?
CB 『Phosphene Dream』をリリースした2010年までオリジナル・メンバーでやってきたけど、その翌年、当時メンバーだったギターのネイト(ライアン)とバンドの関係が悪くなってしまったんだ。全員が一丸となってクリエイティブな方向に向かうのが難しくなって、結局彼は脱退してしまったよ。その後、2012年にギターをやってくれるメンバーを探し始めて、ジェイクに出会ったんだ。翌年にはメンバーとなってくれたよ。ジェイクが加わることで、再びオースティンを拠点として制作活動に希望が出てきたんだ。
ジェイク・ガルシア(以下JG) 僕はこのバンドが始まった時からずっと見てきていて、昔やっていたバンドで対バンでプレイすることもあったんだ。まだ互いのことを知らない頃、ブラック・レベル・モーターサイクル・クラブのライブに僕らが行っていたことがあとになってわかったんだけど……。
CB そうだ! あのライブは重要な出来事だったよ。俺はアレックスと一緒に観に行ったのだけど、あのショウを観てザ・ブラック・エンジェルズを始めたいと思ったんだ。その数年後にバンドのメンバーになる人間がいたっていうのは面白いことだったね。
JG 知り合ったあとのことだけど、ある日バーでビリヤードをプレイしていたらアレックスが“一緒にプレイしてもいいかな?”ってやってきて、“クリスチャンと話していたのだけど、君にギターを弾いてもらいたいんだ”と話を持ちかけられたのを覚えているよ。僕は即座に“グレイトだね! ぜひやってみようよ!”と答え、その晩に一緒にジャムったらかなり良い感じだったんだ。もちろん、慣れるまでに時間はかかったけど、バンドのみんなは僕を快く受け入れてくれたんだ。
ザ・ブラック・エンジェルズは、50〜70年代のロックの中からキャッチーな要素を抽出し、オルタナティブでサイケデリックな独自の音楽表現を追求していると感じます。
CB 50〜60年代のロックは俺のお気に入りなんだ。あの時代はロックンロールがとても革新的だった頃だよね。その時代の音楽を軸に、70年代の一部の音楽をジャンプ台にしてザ・ブラック・エンジェルズは飛び立っている感じだね。中でも60年代がメインになるけど、そこにアップデートされたサウンドを加えている。当時は存在しなかった、最高にクールだと思うペダルを、オールドな機材と組み合わせているんだ。
JG 僕らはかなりのレコード・ファンだから、レコードを入手するたびに新たなインスピレーションを得ているよ。60年代は多くのグレイトな音楽が誕生し始めた時代だからいつ聴いても新鮮だよね。もちろん近年の音楽グループからも影響を受けているからこそ、新しくてクールなペダルを使うことに抵抗はないよ。
バンド名はヴェルベット・アンダーグラウンドの「The Black Angel’s Death Song」から採ったそうですが、彼らからの影響は大きいですか?
CB もちろんさ! ギターを始めた頃、彼らの曲をプレイしながらギターを学んでいったんだ。ミニマムなのにインパクト溢れる強烈なギターのアプローチには衝撃を受けたよ。彼らの1stアルバム(『The Velvet Underground and Nico』/1967年)は俺とアレックスにとって大切な一枚で、小さい頃から一緒に何度もくり返し聴いていた。本当に大きなインスピレーションを受けたね。それからビートルズからの影響もはずせないな。
今のプレイ・スタイルを確立してくれた音楽は何でしょうか?
CB 俺の両親はヒューストンのオールディーズを流すラジオ局をよく聴いていて、ザ・バーズやビートルズ、バディー・ホリー、ロネッツといったアーティストたちの音楽が常に家では流れていたね。10歳の頃に親父が持っていた『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』のアルバムのジャケットを凝視しながら聴いていた経験は、かなりの影響を及ぼしてくれたよ(笑)。
ジェイクはどうですか?
JG 僕は9歳の頃にギターを始めたんだけど、父が持っていた右利き用の5弦ギターを逆さまにして、左利きでプレイしていたんだ。ベンチャーズ、チャック・ベリー、リッチー・ヴァレンスといったクラシックなギター・プレイヤーたちや、B.B.キング、フレディー・キングといったブルース・ギタリストたちに影響を受けていたね。
あなたのプレイ・スタイルを見る限りブルースからの影響もあるのだと思いましたが、小さい頃から様々なプレイヤーに興味を持っていたのですね。
JG そうだね。でもやっぱり50〜60年代のロックンロールが一番好きだったかな。叔父からもらったカセットテープには“50年代のロックンロール”と書いてあって、エヴァリー・ブラザーズ、チャック・ベリー、エディー・コクランといったクラシックなものがたくさん入っていた。僕の父もギター・プレイヤーで、60年代のガレージ・ロックをプレイするようなバンドをやっていたんだ。でも面白いことに、9歳の年のクリスマスに両親は僕にギターじゃなくてベースを買ってくれたよ(笑)。その後、ドラムもプレイしたりしてから、ギターに戻ってきたんだ。
フィーリングがすべてだけど、ジミヘンやピーター・グリーンがやるようにメロディは大事にしたいんだ。
──ジェイク・ガルシア

新作『Wilderness of Mirrors』はどのように制作を進めていきましたか?
CB 過剰に料理するわけじゃなくて、ほど良いフレーバーになるようにマリネしていったような感じだったよね。
JG パンデミックも実は僕たちには良い方向に作用していて、自分たちが求めるサウンドを実験をする時間を与えてくれたよ。二度と経験したくはないけど、僕らは与えられた状況を最大限に活用したってことだね。
CB 今回のアルバムは本当に多くの人たちからの影響を受けていて、例えば、ゾンビーズやキンクス、ビートルズといった60年代のポップ・センスのあるバンドだね。ほかにも、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドやスペースメン3みたいな様々なバンドからインスピレーションを受けて、そこから抽出した音楽要素をブレンダーでごちゃ混ぜにした感じ(笑)。それで俺ら各メンバーのフィルターを通してザ・ブラック・エンジェルらしい音楽に仕上げたというところかな。
新作に収録されている「Firefly」はフレンチ・ポップに感化されてできたそうですね。
CB そうだね。フランス・ギャルの『1968』(1968年)に大きく影響されたところがあるよ。
JG たしかにフランス・ギャルやセルジュ・ゲンスブール、ジャクリーン・タイエブのような、僕らが大好きなフランスのミュージシャンたちの影響が色濃く出ているよね。
ブルージィなソロもありつつ、不気味さをも感じさせる変則的コード・ワークや、轟音の中で煌めくようなリフが特徴的で、それが独自のサイケデリアを確立していると思います。普段、ギター・フレーズはどのように作るのでしょうか?
CB ギターのフレーズを作る時に大きなインスピレーションとなっているのは、やっぱりシド・バレットかな。初期のピンク・フロイドで彼がやっていたことにはとても触発されたよ。そもそも彼は画家としてのキャリアがあって、その影響で俺は大学でグラフィックを学んでいたんだ。彼は“BinsonのEchorecとギターを使って「ペイント」していた”と語っていて、そのアイディアをいただいて普段からプレイしているよ。
俺はテクニカルなギタリストではないけれど、どういったサウンドがグッドなのかを頭の中できちんととらえている。ヘヴィなリフとなると、ジーザス・アンド・メリー・チェインやブラック・レベル・モーターサイクル・クラブを思い浮かべるし、レッド・ツェッペリンでジミー・ペイジがプレイしてきたリフなんて誰もが納得するだろう(笑)? そういうタフなサウンドのフレーズも大好きなんだ。
JG 僕的にはフィーリングがすべてだけど、特にメロディは大切にしているよ。誰もが認めると思うけど、ジミ・ヘンドリックスは僕にとってトップに君臨する大好きなギタリストだ。ファズを効かせたワイルドなサウンドこそ彼の魅力の1つだよね。それから、ピーター・グリーンも僕にとって大きな存在だよ。フリート・ウッドマックのオリジナル・メンバーとしてプレイしてきたものには素晴らしいメロディや音使いがあって、驚異的としか言いようがないんだ。
ピーター・グリーンって彼のギターのハムバッカーのコイルをひっくり返して特別なサウンドを作り出していたよね? これはどこかで聞いた話なんだけど、左利き用のギターってピックアップが上下逆さまになるからコイルがひっくり返った状態でプレイしていることになるらしいんだ。僕とクリスチャンは左利きで、彼と同じサウンドになっているはずなんだよね。
CB それは初耳だよ。グレイトだね! 『Then Play On』(1969年)は名盤だよね。
ちなみに、偶然にも2人共レフティなのは面白いですよね。
JG 誰にも止められなかったからだよ(笑)。
CB 親父がアコースティック・ギターを持っていて12歳の時にプレイしてみようとしたけど、右利き用を上下逆さまにして弾くことに関して誰から何も止められなかったよ。どの教則本を開いても、そんなふうにプレイすることを前提として書かれていなかったから途中で諦めてしまったのだけど、二十歳になった時に誰かから“弦を逆に張れば良い”と教えてもらって、急に世界が開けたんだ(笑)。
JG もし右利きに矯正してプレイしていたら、今とは異なる感じでプレイしていただろうね。左利きでやってきたことを悔やむことはないし、何一つやり直したいと思うことはないさ(笑)。
ファズはショッキングでもあり、美しい道具だと思う。
──ジェイク・ガルシア

楽曲制作の際は、2人でやりとりしてデモに新しいアイディアを取り込むことはありますか?
CB ジェイクが曲のアイディアを作ってくれたら、俺はそれを家で聴いて何かアイディアを重ねていくし、その逆もあるね。俺らはみんながアクセスできるクラウド上のフォルダを持っていて、そこに自由にファイルを入れてみんなでアイディアを共有し合っているんだ。
JG 時にはスマホで録音して、それをメールで送信するだけなんてこともあるよ。かなりシンプルだけど有効だし、やっていて楽しくもあるね。スタジオでの作業って時間を気にしながらやらなきゃいけないことも多くて、そういうことを気にせずにたっぷりと実験的なことをやりたいと思っているから、こういう方法で有効的にアイディアを発展できるのはよかったよ。
アイディアは思いついたらすぐ共有するようにしているのですね。では、“ザ・ブラック・エンジェルズらしさ”と言えるギターのアプローチや音作りのコツはなんだと思いますか?
CB 俺にとって必要不可欠なエフェクトと言えば、リバーブとファズ、エコー、ワウ、それからトレモロ……。なんていうか、“薄気味悪いお化け屋敷”みたいなサウンドを作り出すペダルが好きなんだ(笑)。
JG 僕の場合、結局はギターをプレイする指が重要なんだけど、リバーブはその大きな手助けとなるものなんだ。音に厚みももたらされるというかね。それから、クリスチャンが言う薄気味悪いサウンドを作るうえで、ファズはショッキングでもあり、美しい道具だと思う。ジミ・ヘンドリックスはそういった意味では非常にスリリングな使い方をしていたと思うし、僕もそれに倣いたいんだ。そういったエフェクトを経た末にアンプのスピーカーから生まれてくるギター・サウンドを聴いていると、つい笑顔になってしまうよ。
新作では、冒頭の「Without a Trace」や「History of the Future」などの分厚く凶暴なファズ・サウンドにやられました。
CB あの曲で使っているのは日本製のファズなんだ。
もしかして、Shin-eiのファズですか?
CB そのとおり! Shin-eiのCompanionを使ったんだ。このアルバムの世界観にマッチした音だと思ったよ。
JG スタジオではたぶん50種類くらいのファズを使ってレコーディングをしている(笑)。「History of the Future」では僕は3台のファズを使っていて、ビッグマフを使ったのは覚えているよ。アンプにつないでトーンとボリュームを色々いじっていて、何かグッとくるものがあったら、“じゃあこれでレコーディングをしてみよう!”という感じでやっていったんだ。
サイケデリック音楽は60年代から形を変えながらも、今でも人々を魅了してきています。ギターで表現するサイケデリック・ミュージックの魅力とは何だと思いますか?
CB 実験性で溢れていることだと思うね。いくつものペダルがあって、それらをつなぐ順番を変えても新たなサウンドが生まれる。これがサイケデリックやロックンロールの素晴らしいところだよ。まだ地図に載っていないテリトリーを開拓したり、一般的ではなかったり正しくはないやり方で挑戦してみることが俺らのやりたいことなんだ。
JG 僕らがやる音楽って自由で制約なんて存在しないんだ。これってけっこうスピリチュアルなことでもあると思うんだよね。
本日はありがとうございました。あなたたちがまた来日したら、ぜひ日本版“LEVITATION”を開催したいです!
CB いいね! もちろんさ! 俺らだって何とかして日本へまた行きたいと思っているくらいだ。
JG 僕らの準備はいつでも万端だよ!
作品データ
―Track List―
1. Without a Trace
2. History of the Future
3. Empires Falling
4. El Jardín
5. La Pared (Govt. Wall Blues)
6. Firefly
7. Make it Known
8. The River
9. Wilderness of Mirrors
10. Here & Now
11. 100 Flowers of Paracusia
12. A Walk on the Outside
13. Vermillion Eyes
14. Icon
15. Suffocation
―Guitarists―
クリスチャン・ブランド、ジェイク・ガルシア