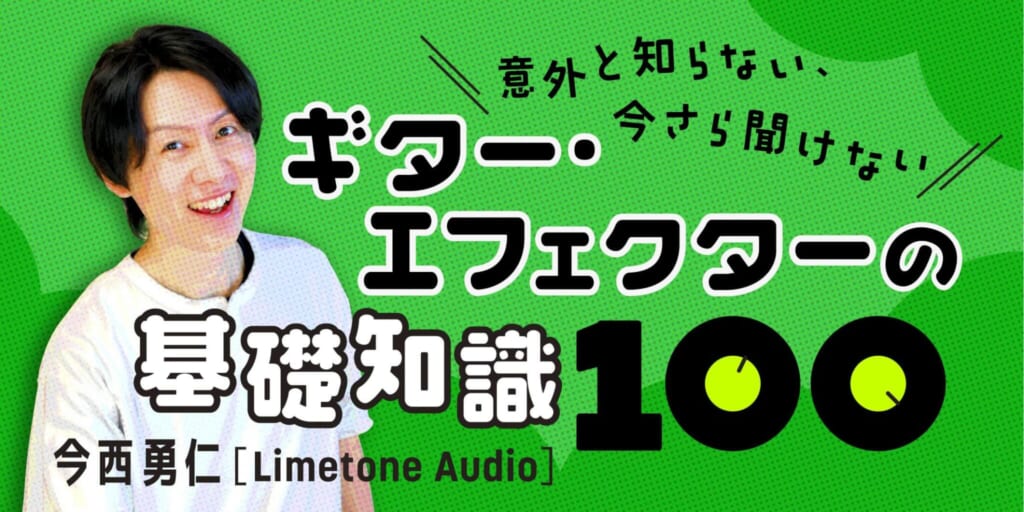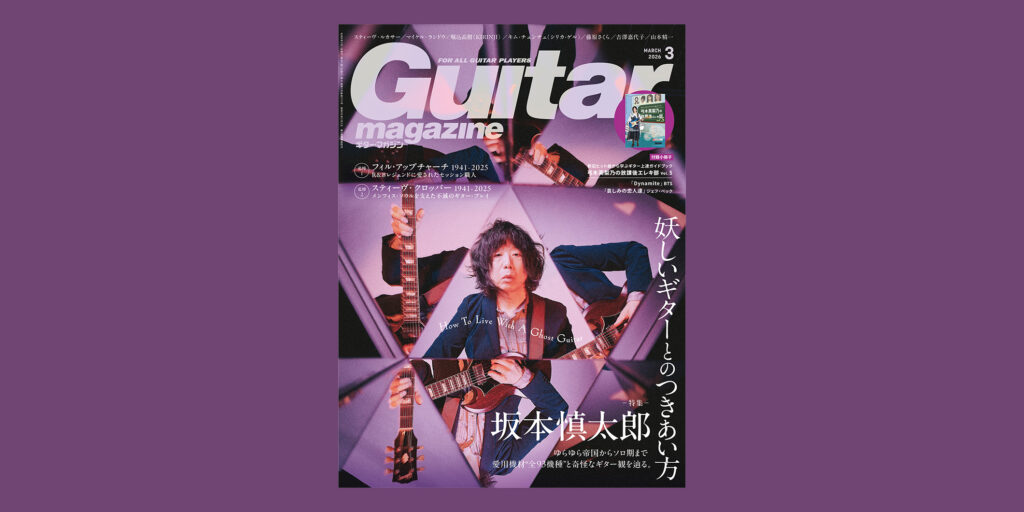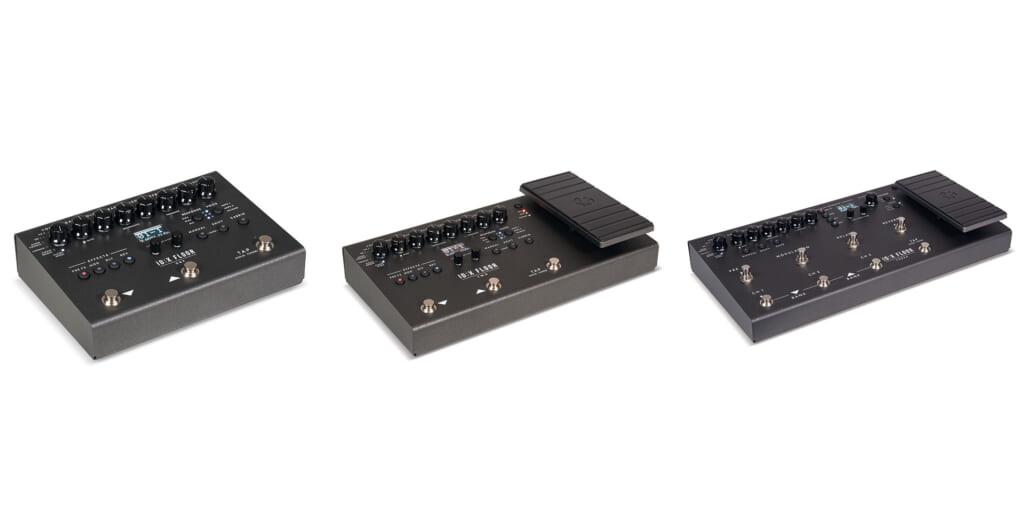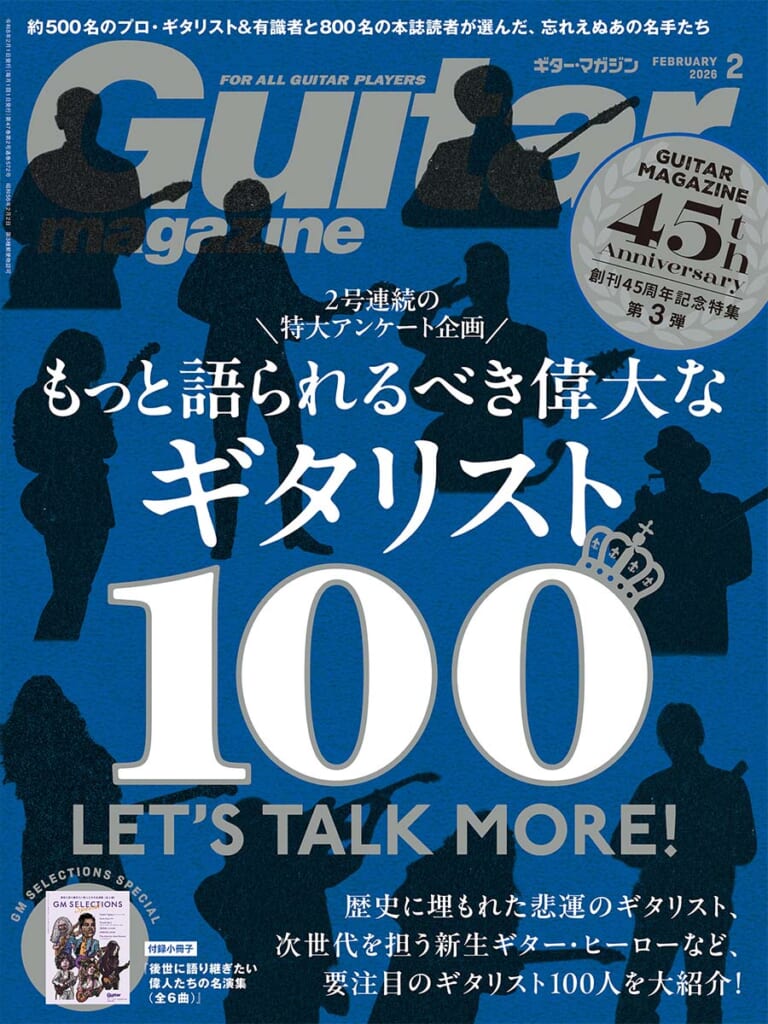個性的な魅力で多くのギタリストたちを虜にする“ビザール・ギター”を、週イチで1本ずつ紹介していく連載、“週刊ビザール”。今回は、現在はアンプで有名な1937年創業の老舗=マグナトーンから、タイフーンを紹介しましょう! ストリーム・シリーズと呼ばれたラインナップの最上位機種に位置する本器が持つ、トーン・スイッチの魔力をとくとご覧あれ!
文=編集部 撮影=小原啓樹 ギター提供=リンテ・伊藤
最上位機種の名に恥じない仕様の1本です。

豊富なトーン・スイッチ
マグナトーンは1937年にロサンゼルスで設立され、蓄音機、エレクトリック・スティール、アンプなどを生産していたブランドだ。特にアンプに関してはバディ・ホリーら草創期のR&Rシーンで使用されるなど、すでにブランドとして一定の地位を確立していた。
エレキ・ギターの製作に着手するのは1956年のこと。名匠ポール・ビグスビーを迎えてデザインされたマーク・シリーズは同社の有名なモデルのひとつである。そして1965年、ナショナルやリッケンバッカー出身のポール・バースがサーフ・ロック市場に向けてデザインした、タイフーン、トルネード、ゼファーの3種からなる“ストリーム・シリーズ”が誕生する。中でもこのタイフーンは最上位機種に位置し、エルヴィス・コステロが使っていたこともあった。
ところで、“西海岸”、“アンプ・メーカー”、“スティール・ギター”、“ソリッド・ギター作りに参入”と聞いて思い浮かぶのが……そう、フェンダーである。設立こそマグナトーンのほうが先だが、その経歴はもろにフェンダーとかぶっているのだ。
ストリーム・シリーズが生まれた65年当時は、上位機種のジャズマスターやジャガーがサーフ・ロック界を席巻しており、同社も相当フェンダーを意識していたに違いない。ただ、満を持して世に送り出したフラッグシップ器だけに、単なる模倣にとどまらない独自の機構も数多い。
興味深いのは、ネック・ジョイント部。ネックの角度を変えられる“マイクロティルト”のような構造が、65年の時点で採用されているのだ。フェンダーがこの仕様を取り入れるのは70年代からなので、構想としてはこちらのほうが早かったということになる。ナットも独特で、指板自体に溝を彫り、その上から金属プレートで押さえ込んでいる。ジャズマスターとほぼ同じ作りと思われるフローティング構造のトレモロ・ユニットも真っ向勝負という感じだ。
そして、最大の特徴となるのがピックアップ下にある3つのトーン・スイッチなのだが……これに関しては世界中の好事家、リペアマンが頭を悩ませている部分でもある。そのわけは下部スライドへ。


マグナトーン タイフーン/1965年製

本記事はギター・マガジン2016年9月号『弾きたいビザール』に掲載された記事を再編集したものです。本誌では、哀愁たっぷりのシェイプを持つ愛しいギターをこれでもかと紹介。好事家のプロ・ギタリストたちが持つビザール・ギターも掲載しています。